【緊急警告】「PayPayで返金します」は99%アウト!──警視庁が警鐘、1.5億円流出を招いた“認証コード詐欺”の全貌とゼロ被害マニュアル
いま何が起きている?
「在庫切れなので PayPay で返金します」
──そんなLINEやSMSが届き、指示どおりに“認証コード”を入力した途端、実はその数字こそが送金額で、知らない相手にお金を丸ごとプレゼントしていた――。
警視庁サイバー対策課によると、2025年上半期だけで認知被害総額は1.5億円超。被害者の年齢層は10代から70代まで広がり、“全世代型キャッシュレス詐欺”と化しています。
1. 被害状況
-
平均被害額:32万円、最大ではほぼ 1,000万円 のケースも確認。
-
消費者庁には「返金のはずが逆送金だった」という相談が3か月で200件超。
-
SNSでは「PayPayで73万円抜かれた…」と実体験ポストが拡散し、注意喚起ツイートが瞬時に数万リポストを記録。
2. 典型シナリオを徹底分解
| ステップ | 詐欺師の動き | 被害者が取らされる行動 |
|---|---|---|
| ①“欠品返金”メール/SMS | 通販サイト名を騙り「銀行返金は不可、PayPayで」と主張 | メッセージに貼られたLINE/QRへ誘導される |
| ②偽サポートが登場 | アイコンも肩書も“公式風”のアカウント | 「では認証コード6桁を入れてください」と指示 |
| ③送金確認を急かす | 「失敗したので再入力」「次は2万円で」など時間差攻撃 | 何度も“認証コード”=送金操作を繰り返す |
ここが最大のトラップ!
PayPayの“認証コード”入力欄は受取側にも送金額がリアルタイム表示されない。焦り+専門用語の少なさが「ただの確認手続き」と錯覚させるカラクリです。
3. ケーススタディ|73万円を失った30代男性の場合
-
フリマで2万円の家電を購入 →「欠品なので返金」と連絡。
-
LINEに誘導され、2,000円の“テスト送金”を指示される。
-
「うまくいかない」と次々金額がエスカレートし、最終的に10回の入力で計73万円が消失。
-
気づいた時には偽アカウントが消え、取引履歴だけが残存。
4. 被害に遭ったら“60分以内”に動くチェックリスト
-
PayPayサポート(0120-990-634)へ即電話し、取引停止・アカウント凍結を要請。
-
送金履歴・チャット画面を全スクショ→クラウド保存。スマホ紛失対策にも。
-
最寄り警察署または #9110 へ被害届。PayPay宛の補償申請に「受理番号」が必須。
-
補償申請は原則60日以内。フォーム入力後に本人確認書類をアップロード。
5. 「PayPay全額補償」の落とし穴と活用術
-
第三者の不正操作と認定されることが条件。自らコード入力した場合も“誘導された”証拠があれば補償対象。
-
スクショ・音声録音・通話履歴が“誘導の証拠”として有効。
-
補償審査の平均期間は2〜4週間。その間に追加被害が出ないよう必ずロック設定を。
6. 今日からできる“詐欺バリア”5カ条

-
「返金はPayPayだけ」は即違和感——公式ショップは銀行振込やカード返金も併用。
-
SMS・メールのリンクは踏まない——PayPay公式は“paypay.ne.jp”ドメインのみ。
-
公式アプリ内で通知確認——アプリ→取引履歴→メッセージで真偽を瞬時に判別。
-
“今すぐ操作しないと損”は深呼吸——時間制限は詐欺師の定番プレッシャーワード。
-
家族&友人のグループチャットで共有——高齢者や未成年の“知識ギャップ”を埋める共助が最強。
✍️ まとめ|“疑って→確認して→行動”のワンテンポが命綱
キャッシュレスは便利さと裏腹に、“ワンタップで大金が動く”リスクもはらみます。
覚えておく一言
「返金手続きで“認証コード”は絶対に打たない!」
警視庁や消費者庁は「手口がさらに巧妙化する」と見ています。
今日この記事を家族にシェアし、“ワンテンポ置く習慣”を全世代で徹底しましょう。備えこそが、あなたのPayPay残高を守る最強のセキュリティです。




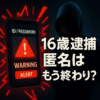
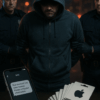
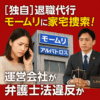
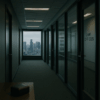




最近のコメント