【背筋ゾクゾク】怪談の日(8月13日)に聴きたい!戦慄の怪談3選と百物語のやり方
🔥とりコレ3行まとめ
-
夏の定番“怪談の日”にピッタリなおすすめ怪談を3つ厳選!
-
怖いけど魅力的なリアル系・古典系の話を紹介
-
怪談の定番「百物語」のやり方と必要な道具もわかる!
もう聞いた?怪談の日って実は8月13日!
8月13日、実は“怪談の日”と呼ばれているのを知っていますか?
由来は、1995年に稲川淳二さんの怪談番組が放送されたことにちなんでいます。夏といえば怪談、というイメージもここから強くなったとされています。
怖い話って聞きたくなるけど、ただ「怖い」だけじゃ物足りないですよね。
この記事では、ちょっと変わった怪談や、みんなでワイワイ楽しめる「百物語」のやり方まで網羅!背筋がゾクっとするだけじゃない、“心地よい恐怖体験”をあなたにお届けします。
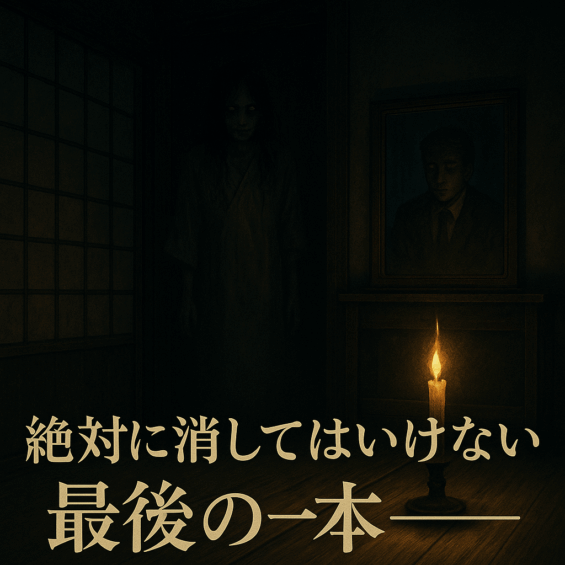
夏にピッタリ!おすすめ怪談3選
1. 【実話風】壁の中から…赤いクレヨン
引っ越してきたばかりの家で、小さな子どもが「赤いクレヨンが欲しい」と言い出す。
そんなクレヨン、買っていないのに?ある日、壁のリフォームを始めると、隠し部屋が発見され、中には「ゴメンナサイ」と何度も書かれた赤いクレヨンの文字…。
この話の怖さは、現実的な設定と“誰にでも起こり得そうな”シチュエーション。
「何も起きてないのに怖い」系が好きな人にぴったりです。
2. 【江戸の復讐譚】四谷怪談
日本三大怪談のひとつ「四谷怪談」。
裏切られ、毒を盛られて亡くなった妻・お岩の怨霊が、夫とその愛人に復讐を果たすという物語です。
ポイントは「見た目の恐怖」と「人間の闇」。
演劇や映画でも繰り返し描かれ、日本人の心に深く根付いている定番中の定番です。
3. 【シュールで不気味】足洗邸の怪
江戸の町・本所に伝わる“七不思議”の一つ。
夜な夜な天井から巨大な足が降りてきて、「足を洗え」と命じられる。洗わないと…?
怖さというより、「なんで足?」という不条理さと、不気味なインパクトがウリ。
話のインパクト重視の人には最高です。
みんなでやってみる?「百物語」のやり方ガイド
💡百物語って何?
百物語は、昔の日本で行われていた“怪談の儀式”的な遊び。
100本のろうそくを灯し、1話ずつ怪談を語っていき、話すたびに1本ずつ消していくという流れです。
100話目を話し終え、最後のろうそくを消すと“何か”が現れる…という都市伝説的なルールもあり、スリル満点!
🔧準備するもの
-
ろうそく(本格なら100本、簡易版なら10〜20本でOK)
-
ロウソク立てや火消しグッズ(安全対策は忘れずに)
-
懐中電灯やスマホライト(暗闇に慣れるためにも)
-
怖い話のストック(ネットや本から事前に選んでおこう)
-
鏡(本格派は中央に鏡を置いて“霊が映るかも…”という演出を)
👻やり方(10本バージョン)
-
暗い部屋にろうそくを10本並べて灯す
-
一人ずつ順番に怪談を話す
-
話し終えたら、1本ずつロウソクを消していく
-
最後の1本をあえて残すのが“安全圏ルール”
-
儀式が終わったら、お清めに手を洗ったり、明るい部屋に移動しよう
怪談を楽しむためのちょっとしたコツ
怖さのバランスが大事
リアルな話ばかりだと、心が重くなってしまうことも。
1つリアル系、1つファンタジー系、1つ笑える怪談を混ぜて、バランスよく楽しむのがおすすめ!
終わったあとは「お清め」で気分転換!
「本当に霊を呼んじゃったかも…」と不安なときは、以下を試してみて。
-
塩を撒く(玄関・部屋の四隅など)
-
白いご飯を一口食べる
-
明るい音楽をかける
子どもと一緒にやるなら?(自己責任)
-
怖さ控えめの話にする
-
ろうそくの本数は少なめに
-
安全第一!火の管理をしっかり
【まとめ】怪談の日は“楽しく、怖く、安全に”
-
怪談の日は、一年に一度の“涼しさ体験デー”!
-
赤いクレヨンや四谷怪談など、タイプ別で話を選ぼう
-
百物語はライトにやっても十分楽しい
-
安全対策と気分転換も忘れずに!
怪談は“怖さを楽しむ”文化です。無理せず、自分に合ったレベルで楽しんでくださいね!
今年の8月13日は、友達と一緒に忘れられない夜にしよう。

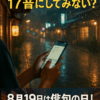

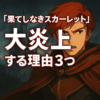
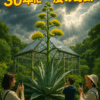







最近のコメント