【暴力と指導を混同する指導者がおかしいだけ】広陵高校ハラスメント事案“明日は我が身”で逃げる指導者こそ問題
とりコレ3行まとめ
-
広陵高校での暴力・性加害告発が、高校野球界の古い指導体質を露呈。
-
「明日は我が身」発言は責任回避の言い訳でしかない。
-
暴力と教育の線引きができない指導者は、もはや現場に立つ資格なし。
「明日は我が身」じゃなくて「暴力をやめろ」が先だ
今年、甲子園常連校・広陵高校野球部で発覚した一連の暴力・性加害告発は、日本の高校野球にとって避けて通れない問題を突きつけました。
発端は寮内でのルール違反を口実にした上級生から下級生への暴力行為。日本高野連は3月に「厳重注意」の処分を下しましたが、そこで終わりではありませんでした。
SNSでさらに深刻な証言が拡散され、性加害、熱湯をかける、暴言、日常的なハラスメントなど、想像を超える行為が次々と明るみに出ます。被害届の提出、第三者委員会による調査が進む中、世間の視線は厳しくなる一方です。
そんな中、ある甲子園出場監督が口にしたのが「指導者のほとんどが明日は我が身と感じている」という言葉。
この一言が炎上の火種になりました。「自戒のつもりかもしれないが、責任逃れの予防線に聞こえる」「暴力を防ぐ覚悟がない証拠だ」という批判が噴出。
今必要なのは、“明日は我が身”と怯えることではなく、“暴力は絶対やらない”という当たり前の覚悟です。

暴力と指導を混同する“昭和思考”の危険性
高校野球は、華やかな甲子園の裏で、いまだに「厳しく叩けば伸びる」という昭和の根性論を引きずっている現場があります。
この文化の本質的な危険は、暴力を「愛のムチ」と言い換えて正当化し、被害を受けた生徒に「我慢すれば成長できる」という歪んだ価値観を植え付けることです。
結果、加害側は「自分もやられたから当然」という思考停止、被害側は「言っても無駄」と声を飲み込む負の連鎖が続きます。
広陵のケースも、部内の閉鎖的な上下関係や寮生活が、異常行為を外部から隠しやすくしていました。
SNSで初めて被害の一部が可視化された事実は、「現場の自己完結」では問題が解決しない証拠です。
もし告発がなければ、この“暴力指導”は今も続いていたかもしれません。
「明日は我が身」発言が甘すぎる理由
一見、警戒や謙虚さを示すように見える「明日は我が身」という言葉。
しかし教育現場でこれを口にする場合、多くは「自分だって間違えるかもしれない」という甘い自己正当化にすり替わります。
この思考は、暴力やハラスメントを“事故”や“うっかりミス”として処理する土壌を作ります。
結果、責任を取らない指導者が生き残り、本当に現場を変えるべき人間が淘汰される悪循環が生まれます。
もし本当に明日は我が身と危機感を持つなら、今すぐやるべきことは決まっています。
-
暴力と指導の境界を明文化
-
第三者による監視・相談窓口を設置
-
定期的な研修で価値観をアップデート
口先だけの警戒では、再発防止には1ミリも役立ちません。
再発防止に必要な3つの改革
-
透明性の確保
問題が発覚したら即公表。隠蔽すればSNSで拡散され、信頼は完全に失われます。 -
暴力禁止の明文化と研修
指導者全員に暴力・ハラスメント禁止のガイドラインを渡し、年1回以上の研修を義務化。
「これはセーフ」はなし。曖昧さをゼロにすることが大事です。 -
被害者第一の対応
加害側の“指導の意図”よりも、被害者の安全と回復を最優先にする文化を作る。
これがなければ、同じ悲劇が何度も繰り返されます。
まとめ
「明日は我が身」という言葉に安心している指導者は、今すぐ考えを改めるべきです。たしかに指導に熱が入れば厳しく接することも必要なのは間違いありません。
ただ、暴力と指導は絶対に別物。
線引きができないなら、その瞬間に指導者失格です。部のためチームのためなど偉そうなこと宣う前に早急に職を辞するべきでしょう。
広陵高校の事案は、一校だけの問題ではなく、日本のスポーツ教育全体が抱える構造的な欠陥の縮図。
未来の選手たちが安心して全力を出せる環境を守るため、大人が“本気で”変わる時が来ています。
参考・引用記事
-
「指導者のほとんどが明日はわが身と感じているんじゃないですか…」広陵の“暴力事案”が…
https://www.ronspo.com/articles/2025/2025081001/ -
広陵高校暴行・性加害告発に新証言、中井哲之監督…波紋止まず
https://coki.jp/article/column/56791/


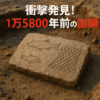
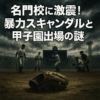
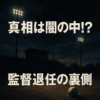
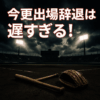
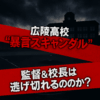
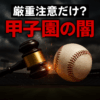




最近のコメント