【群馬リアル】“共生”は無理?「日本人ファースト」浮き彫りの本音
とりコレ3行まとめ
-
群馬・大泉町では外国人が2割超、その中で「共生」のリアルな課題が見えてきた
-
「日本人ファースト」支持の背景には“文化やルールを守らない外国人”への不満も
-
ただし一方で、日本に合わせて努力してきた外国人の苦悩も存在する
今、群馬で何が起こってる?
最近の選挙で注目を集めたのが「日本人ファースト」を掲げる参政党。SNSを中心に若い世代の支持も広がり、「日本を日本らしく守ろう」というメッセージは、地方にも響いています。
特に群馬県大泉町は、日本有数の“外国人タウン”。人口の2割以上が外国籍で、日常的にポルトガル語やスペイン語が飛び交う独特の街並みです。表向きには「共生モデル」として評価される一方、実際の住民からは「文化を尊重しない外国人が多すぎる」「ルールを守らない人とは暮らせない」といった本音も聞こえてきます。
この“共生のひずみ”が、参政党支持の広がりと重なっているのです。
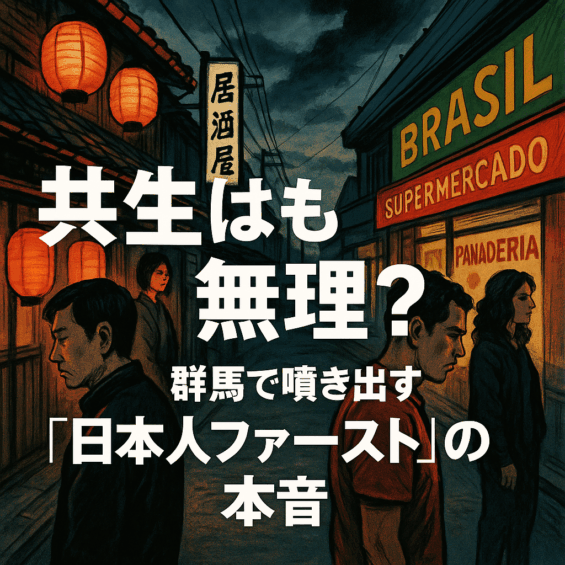
群馬の「共生」の現実
まず前提として、群馬・大泉町の共生事情を整理しておきましょう。
大泉町には自動車関連の工場が集まり、1980年代から外国人労働者が増加しました。特に日系ブラジル人やペルー人が多く、町のスーパーでは海外の食品が普通に並び、街中にはポルトガル語の看板も目立ちます。
一見すると国際的でにぎやかな雰囲気ですが、住民同士の価値観の違いが摩擦を生んでいるのも事実です。
例えば「夜中に大音量で音楽を流す」「ゴミ出しルールを守らない」「公共マナーが違う」といった小さなトラブルが積み重なり、地域社会のストレスになっています。
こうした背景が、「やっぱり“共生”は簡単じゃない」という声につながっているのです。
「日本人ファースト」に対する外国人の声
参政党が掲げる「日本人ファースト」というスローガン。これに対して、現場に住む外国人たちはどう感じているのでしょうか。
◆「努力してきたのに、ひとくくりにしないでほしい」
ブラジル出身で群馬に長年暮らすヤマカワ・フォリア・ナタリア・レイコさんは、日本で育った子どもを持ち、自身も地域に溶け込む努力をしてきました。
「税金も払ってきたし、日本人と同じように生活しているのに、外国人は犯罪者扱いされる。全部をひとくくりにするのは不公平」と不満を漏らします。
彼女の言葉には、“文化を尊重している外国人”の立場からの切実さがにじみ出ています。
◆「ルールを守ってきたのに“自分勝手”と言われるのは辛い」
伊勢崎市でカレー店を営むリズワン・ウル・ハックさんも、日本社会に合わせて努力を続けてきた一人。
「日本は時間に厳しい国だから、自分は必ず早めに行動してきた。日本人と同じようにマナーも守っている」と語ります。
それでも「日本人ファーストの考えはselfish(自分勝手)だと思う」と反論。努力をしてきた外国人にとっては、“全員まとめて否定される”ような空気がつらいというのです。
なぜ「共生は無理」という声が出るのか?
一方で、地元の日本人からは「共生はもう限界」という声も少なくありません。
理由はシンプルで、「日本文化やルールを尊重しない外国人が目立つ」から。
ゴミ出しや騒音、交通ルールなど、生活の基本を守らない人がいると、地域の信頼関係は一気に崩れます。そのイライラが「もう外国人とはやっていけない」という感情に直結しています。
SNSでは「外国人は権利ばかり主張して義務を果たさない」という投稿も見られ、そうした空気が参政党の「日本人ファースト」の支持拡大を後押ししている面もあります。
読者の疑問に答えるQ&A
Q1. どうして参政党が若者に支持されるの?
→「シンプルでわかりやすいメッセージ」が理由です。「日本を守る」という旗印は強い言葉で、SNS世代には特に響きやすいのです。
Q2. じゃあ共生はもう無理なの?
→完全に無理ではありません。実際にルールを守り、日本社会に溶け込んでいる外国人も多くいます。問題は「一部のマナーを守らない人」の行動が、全体の評価を下げている点です。
まとめ
群馬・大泉町や伊勢崎で見えたのは、“きれいごとだけでは済まない共生の現実”。
「文化やルールを守らない外国人とは一緒に暮らせない」という日本人の本音もあれば、「努力してきたのにひとくくりにされるのは辛い」という外国人の叫びもある。
結局のところ大事なのは、「日本人ファースト」か「外国人ファースト」かという極端な選択ではなく、お互いがルールを守り文化を尊重する“歩み寄り”です。
共生は簡単じゃない。でも、それを直視しないと未来は開けないのかもしれません。
参考・引用記事
-
朝日新聞「外国人と共生『簡単じゃない』 参政党票が上回った『優等生』の本音」 https://www.asahi.com/articles/AST7V151XT7VUTIL034M.html
-
TBS NEWS DIG「“外国人”と生きる保守王国・群馬で聞いた参政党『日本人ファースト』への思い」 https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2111250?page=2
-
Wikipedia「Sanseitō/参政党」 https://en.wikipedia.org/wiki/Sanseit%C5%8D
-
Wikipedia「2025年日本參議院選舉」 https://zh.wikipedia.org/wiki/2025%E5%B9%B4%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%83%E8%AD%B0%E9%99%A2%E9%81%B8%E8%88%89

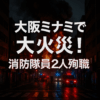
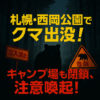
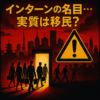
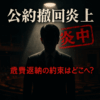
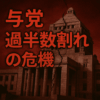

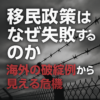




最近のコメント