【中国依存脱却】パンダロスで宿泊1万人減!白浜が挑む“本当の観光力”再生計画
とりコレ3行まとめ
-
白浜の宿泊者数が前年比で1万人減少、原因は“パンダロス”。
-
町長は「パンダに頼らない観光戦略」へシフトを宣言。
-
温泉・自然・高級ホテル・新アクティビティで再起を狙う。
パンダがいなくなった白浜に異変!宿泊客1万人減の衝撃
和歌山県白浜町といえば、「日本でパンダが見られる町」として全国的に有名でした。アドベンチャーワールドには長年ジャイアントパンダが滞在し、その可愛らしさと希少性から観光客を呼び込み続けてきました。
しかし、2023年以降にパンダが中国へ返還され、白浜から“パンダ”という最大の目玉が消えました。そして2025年7月、宿泊者数が前年同月比で約1万人減少するというショッキングな数字が公表されたのです。
観光関係者の間からも「やっぱりパンダ目当ての人が多かった」という声があがっており、数字がそれを裏付けています。

白浜は“パンダ依存”だった?経済効果は驚きの1,256億円
実際、白浜がパンダにどれほど依存していたかを示すデータがあります。
関西大学の宮本勝浩名誉教授によると、パンダが滞在していた約31年間での経済効果は約1,256億円にものぼるとされています。
さらに、観光客の約2割がパンダを目的に訪れていたと推計されており、1人あたりの消費額はおよそ2万5,000円。単純計算でも年間150億円規模の波及効果を生み出していたといわれています。
海外メディアの試算では、パンダがいなければ観光客が年間20万人減少し、最大で年間60億円規模の収益損失になる可能性があるとも指摘されています。
ここまで数字を見ると、「パンダがいなくなったらどうなるの?」という町の不安が現実になってきているのは明らかです。
町長が宣言「パンダのせいにしない!」脱パンダ戦略の幕開け
ただし、町長は危機感を抱くだけでは終わっていません。白浜町の大江町長は、「パンダがいなくなったから客が減った、という言い訳を断ち切る」と強い言葉で表明しました。
その背景には、白浜が本来持っている観光資源の豊かさがあります。
白良浜の真っ白な砂浜や温泉、三段壁や千畳敷の絶景など、パンダ以外にも全国レベルで通用する観光資産が数多くあります。
また、町は積極的に新たな観光の柱を育てようとしています。
-
白良浜に期間限定のビーチバーをオープン
-
高級5つ星ホテルの誘致を進行中
-
インバウンド需要を取り込むための空港強化
-
アドベンチャーワールドの「動物×体験型」施設拡充
こうした取り組みによって、町全体を「パンダがいなくても楽しめるリゾート地」として再ブランディングする流れが進んでいるのです。
白浜が若者を呼び戻すための“新コンテンツ”とは?
今後の白浜観光で注目すべきは「若い世代をどう取り込むか」です。10〜30代は旅行先を選ぶとき、インスタ映えや体験型コンテンツを重視する傾向があります。
白浜はそのニーズに対応し始めています。
-
ビーチバーやパラソル付きシートなど「写真映え」する施設
-
グランピングやキャンプ場といったアウトドア体験
-
アドベンチャーワールドのイルカショーやサファリ体験の強化
-
高級リゾートホテルでのラグジュアリー体験
特に、海や動物といった非日常的な体験は、SNSとの相性が抜群。パンダに頼らなくても「行きたい!」と思わせる力は十分にあるのです。
インバウンド需要も大きな武器に!
白浜にはもうひとつの強みがあります。それは海外からの観光客(インバウンド)です。白浜空港の利用者数は年々増え続け、2024年度は過去最高の23.5万人を突破しました。
外国人旅行客にとっても、白良浜の海や温泉文化は大きな魅力。今後は海外向けの情報発信を強化すれば、アジア圏を中心に観光需要をさらに広げられる可能性があります。
まとめ:パンダがいなくても白浜は進化できる!
-
白浜は2025年7月に宿泊者数が1万人減少し、“パンダロス”が数字に表れた。
-
しかし、町長は「パンダのせいにしない」と宣言し、新しい観光戦略をスタート。
-
温泉、絶景、ビーチアクティビティ、高級ホテル、動物体験など、多様な魅力が白浜にはすでに存在する。
-
SNS世代やインバウンドを取り込む戦略によって、パンダなしでも成長する余地は十分にある。
パンダはもういない。
でも白浜は“終わり”じゃなく、むしろ“新しい始まり”を迎えているのかもしれません。

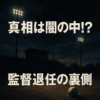
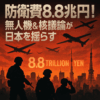
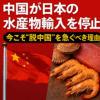



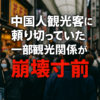




最近のコメント