【総裁選前倒し/解散】選挙で民意はNOを突き付けた! 石破首相は退陣を
とりコレ3行まとめ
- 参院選で与党は過半数割れ。なのに首相は続投アピール。
- 党内は「総裁選の前倒し」を本格手続きへ。副大臣まで賛成の動き。
- それでも「解散ちらつかせ」で抑え込み? 大義なき一手は逆効果です。
いま何が起きてる?
7月の参院選で自民・公明は過半数割れでした。
それでも石破首相はテレビ各局で続投の意向を明言。ところが自民党内では、「総裁選を前倒しでやるべきだ」という声が一気に増え、選管が賛同議員名の公表まで含めた手続きに踏み込みました。
さらに一部報道では、首相周辺から「前倒しなら解散」をにおわせる話も浮上。
——選挙でNOが出た直後に、解散カードで党内を黙らせる。これはさすがにみっともないです。政治の信頼を守るなら、潔く退くほかありません。
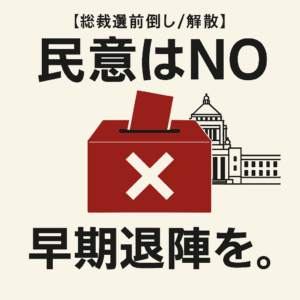
まずは事実関係をサクッと整理
-
参院選の結果:改選125のうち、与党は自民39+公明8の計47議席にとどまり、非改選を含めても参院で過半数割れ。
-
首相の姿勢:選挙当夜、テレビ番組で「続投」の考えを明確化。
-
党内の動き:自民の総裁選挙管理委員会が、前倒し実施の賛否を“書面”で確認し、賛成議員と賛成した都道府県連の公表方針まで決定。9月上旬にも意思確認へ。
-
“賛成”の広がり:若手・中堅に加え、副大臣クラスからも「前倒し賛成」「必要なら辞任」の声。
-
世論の空気:前倒し論そのものに失望44%という調査結果も。
(以上はロイター、Bloomberg、テレ東BIZ、福井新聞、朝日、KSIの調査など複数報道を総合)
「解散ちらつかせ」はなぜ最悪手なのか
解散権は首相の専権であっても、使うには大義が要ります。
選挙で審判を受け、参院で少数与党になった直後に「脅し」のように解散を見せるのは、有権者の審判を軽く扱うサインに見えます。
さらに、「前倒しを言うなら解散だ」という空気は、党内議論の萎縮を招き、結果的に政治不信を深めます。
10〜30代の読者目線でいえば、「負けたのに居座る→不満→また選挙のカード」というループは、税金も時間も消費するだけ。コスパ最悪です。
前倒しのルールを噛み砕き解説
-
仕組み:自民党則では、党所属国会議員+都道府県連代表の過半数(=172以上)が要求すれば、任期途中でも臨時の総裁選を実施できます。
-
やり方:今回は書面で意思確認。議員は記名・押印の書面を本人が本部へ提出。都道府県連は機関決定が必要。提出者名は公表へ。
- タイムライン:9月2日に参院選の総括→その後、5〜7日内をめどに提出期日を設定→過半数に達すれば前倒し決定。
これ、ルールに沿った透明プロセスです。ここを飛ばして「解散で牽制」は、手続き無視に見えます。
党内と世論の“温度差”を押さえる
-
党内は「賛成派」「慎重派」「様子見」に分裂。朝日の議員アンケートでは約8割が態度保留。
-
一方で、副大臣が辞任覚悟で賛成と表明するなど、動きは加速。
-
世論は「前倒しゲーム」に冷めた目。KSIの調査では「失望44%」。
-
それでも内閣支持は一部で上向き。ここが「前倒し派VS続投派」の綱引きポイントです。
だからこそ、首相自身が「身の処し方」を早く示すことに価値があります。迷い続けるほどコストが増えます。
早期退陣こそ、最短の“信頼回復”
-
参院で過半数割れ=民意の明確なシグナル。
-
前倒しの手続きが動き出し、副大臣まで賛成の流れ。
- それでも「解散ちらつかせ」で延命を図れば、“大義なき権力維持”の印象が決定打になります。
政治の信頼を立て直す最短距離はシンプルです。
——潔く、早急に身を引くこと。
それが与党にも、野党にも、そして有権者にも一番わかりやすく、次の一歩につながります。
この記事の活用ポイント
-
「いつ何が決まるの?」
→ 9月上旬に意思確認、過半数で前倒し決定。そこで首相の進退も実質的に動きます。 -
「結局、解散はある?」
→ 法的には可能。ただし大義が問われ、逆風リスクが高い。 -
「市場や生活への影響は?」
→ 政治の迷走は政策遅延と不確実性を生み、物価・賃上げ・減税議論など暮らしの判断に直撃します。だからこそ早決着がベターです。
まとめ
参院選で示されたNOを直視せず、解散カードで党内をねじ伏せる政治はもう古いです。
手続きに沿って淡々と前倒しを進め、トップは責任を取る。それだけで政治はグッと健全化します。
若い世代の「政治ってわかりにくい」を減らすにも、ここでけじめを。
参考・引用記事(一次・準一次情報/順不同・一部有料含む)
-
参院選、自公で過半数に届かず 石破首相は続投表明(Reuters)
https://jp.reuters.com/world/japan/SMUFQIAUBBKBDAGF4GPTYFVKUM-2025-07-20/ -
石破首相が続投の方針、「日本の将来に責任」 参院選で過半数割れ後も(Reuters)
https://jp.reuters.com/world/japan/OHJYVXGG3BIPRLJFJUI3NYRZCI-2025-07-20/ -
自民きょう参院選総括、森山幹事長の進退が焦点-総裁選前倒しで攻防(Bloomberg)
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-09-01/T1W1Y8GOT0K400 -
自民総裁選前倒しは9月上旬にも意思確認へ、要求者名を公表-逢沢氏(Bloomberg)
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-08-27/T1LDSPGP9VCW00 -
斎藤財務副大臣、自民党総裁選の前倒しに賛成-辞任覚悟も(Bloomberg)
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-08-31/T1U7PXGOYMTC00 -
自民総裁選の前倒し 要求議員名を公表へ(テレ東BIZ)
https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/nms/news/post_324805 -
自民・総裁選管が初会合 総裁選“前倒し”是非 書面で確認へ(テレ東BIZ)
https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/nms/news/post_324268 -
自民党総裁選是非、書面で確認へ(福井新聞ONLINE)
https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/2386798 -
自民・小林鷹之氏 首相が辞任しなければ総裁選前倒しに「署名」(朝日新聞デジタル)
https://www.asahi.com/articles/AST8Y3VD9T8YUTFK01HM.html -
総裁選前倒し、自民議員8割賛否明かさず 賛成回答40人(朝日新聞デジタル)
https://www.asahi.com/articles/AST8W02FYT8WUTFK00PM.html -
報ステ大越健介氏「トップの進退に直結する話」総裁選前倒しめぐる自民執行部の手法に一定理解(日刊スポーツ)
https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/202509020000114.html -
自民の総裁選前倒し議論に「失望」44%(紀尾井町戦略研究所/調査発表)
https://ksi-corp.jp/topics/survey/2025/web-research-99.html -
自民の総裁選前倒し議論に「失望」44%(PR TIMES転載・EXCITE)
https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2025-08-28-65702-119/ -
総裁選前倒し巡り焦る首相、「衆院解散」ちらつかせ抑え込みに躍起…党内反発「どこにも大義ない」(Yahoo!ニュース)
https://news.yahoo.co.jp/articles/8526c56bb442c03c9bd30512f01c97b404c3ab8

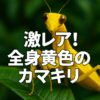
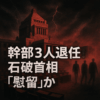
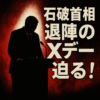
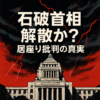
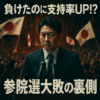





最近のコメント