【スマホ料金なぜ値上げ?】ドコモ・au・Y!mobileの最新事情と対策5選
とりコレ3行まとめ
-
ドコモ・au・Y!mobileが次々に料金改定を発表。値下げ競争は完全にストップ。
-
背景には電気代や人件費の上昇、5G・コンテンツサービスなどへの投資がある。
-
ただし「割引条件を満たす人」と「そうでない人」で負担額に大きな差が出る仕組み。
スマホ大手、続々と「値上げ発表」の現実
2025年は、スマホ料金に大きな変化が訪れています。
-
ドコモは新プラン導入を6月にスタートし、報道では「主要プランで月額1,000円以上の値上げになる可能性がある」とされています。公式発表では付加価値を強調しており、詳細な値上げ額は示していませんが、ユーザーの負担増は避けられない見通しです。
-
au(KDDI)も8月からプラン改定を実施。報道では「220円〜330円程度の引き上げ」とされています。こちらも公式発表では料金改定を明言しているものの、プランごとの増額幅は細かく示されていません。
-
Y!mobile(ソフトバンク)は9月25日から「シンプル3」を開始。Sプランはデータ容量を4GB→5GBに増量する一方で、料金は2,365円→3,058円(税込)へ。ただし「PayPayカード割」「おうち割 光セット(A)」といった割引が強化され、条件を満たせば実質的な値上げを避けられる場合もあります。
さらに、ドコモは9月から店頭での事務手数料を加算方式に変更しました。今後、オンライン手続きとの料金差が広がることが予想されます。

なぜ一斉に「値上げ」へ?
数年前までの携帯料金は「政府の値下げ要請」を背景に、値下げ競争が繰り広げられていました。
ところが、ここにきて流れは完全に逆転しています。その理由を整理すると次のとおりです。
1. 電気代・人件費の上昇
スマホの通信を支える基地局は24時間稼働。電力コストの増加と人件費の高騰が重くのしかかっています。
各社が「採算確保のための見直しが不可避」と判断するのは自然な流れです。
2. 5Gやコンテンツへの投資
単なる通話やデータ通信だけでなく、動画配信(DAZNなど)やAmazonプライム割引、海外ローミング特典など「付加価値」を含めたプランが広がっています。
サービスを盛り込むことで見た目の魅力を高めつつ、料金は底上げされています。
3. 値下げ圧力の一段落
2020年以降の「料金4割値下げ」ムードが落ち着き、各社は採算を重視する方向に回帰しました。
「競争」から「収益確保」へ舵を切ったのです。
4. 割引条件を利用できるかで差が出る
Y!mobileのように「基本料は上げるが割引を増やす」方式が広がっています。
結果として、条件を満たす人は従来と変わらないか安くなる一方、割引を利用できない人は大幅に負担増。実質的に「二極化」が進んでいます。
5. サポート体制の有料化
ドコモのように店頭や電話窓口での事務手数料を引き上げる動きも出ています。
今後、オンライン手続きが「安い選択肢」として定着しそうです。
値上げ時代にどう対処する?5つの節約ポイント
スマホ料金が上がる流れの中でも、私たちができる工夫はあります。
-
割引をフル活用
家族割・光回線・電力サービス・カード割引など、条件を揃えれば料金はまだ下げられます。Y!mobileでは割引後に1,000円を切るケースも。 -
自分のデータ使用量を把握
「毎月20GB必要だと思っていたけど実際は10GBしか使っていなかった」という人は多いです。余計なプランを選んでいるとそれだけで数千円の無駄。 -
オンライン手続きで節約
店頭だと事務手数料が割高に。機種変更やプラン変更は可能な限りオンラインで。 -
付加価値サービスは必要か見極める
DAZNや海外ローミングなどを使わない人にとっては「宝の持ち腐れ」。最小限のプランに絞ったほうが結果的に安く済みます。 -
他社への乗り換えも視野に
すべてのキャリアが同じタイミングで値上げするわけではありません。競合の動きが緩やかなうちに乗り換えることで、月数千円の差が出ることもあります。
よくある疑問にサクッと答える
Q:ニュースで“一斉値上げ”と聞いたけど、全員が値上げされるの?
→ 基本料金は上がっていますが、割引を使える人は従来通りか、場合によっては下がることもあります。割引を使えない人ほど負担が増える仕組みです。
Q:本当に値上げの理由って正当なの?
→ 電気代や人件費の高騰、そして5Gやコンテンツ投資の必要性は事実。企業としては避けられない部分もあります。
Q:今すぐできる節約は?
→ まずは自分のデータ使用量を確認。それから「割引条件を満たせるか」を整理し、オンラインでプラン変更するだけでも効果があります。
まとめ
スマホ料金の「値下げ競争」は終わり、これからは「値上げ前提」の時代です。
ただし、全員が損をするわけではなく、割引・プラン最適化・オンライン活用によってまだ十分に節約できます。
黙って値上げを受け入れる時代ではありません。自分に合った戦略を取ることで、月々の負担を最小限に抑えることができます。
参考・引用記事一覧
-
NTTドコモ「お客さまのさまざまなニーズにお応えする新料金プラン『ドコモ MAX』『ドコモ ポイ活 MAX』『ドコモ ポイ活 20』『ドコモ mini』を提供開始」
https://www.docomo.ne.jp/info/news_release/2025/04/24_00.html -
TBS NEWS DIG「NTTドコモが新料金プラン発表 主要プランは月額1000円超値上げも」
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1875522 -
KDDI「料金プランのサービス内容と月額料金の改定について」
https://www.au.com/pr/renewal2025/ -
KDDI(法人)「auの料金改定に関するお知らせ(主なプラン改定一覧)」
https://biz.kddi.com/support/user/charge-renewal2025/ -
ソフトバンク「“ワイモバイル”の新料金プラン『シンプル3』を提供開始」
https://www.softbank.jp/corp/news/press/sbkk/2025/20250904_01/ -
Business Insider Japan「ドコモとauが起こした料金プランの『値上げ旋風』。競合のソフトバンクと楽天が追随しづらい理由」
https://www.businessinsider.jp/article/2505-mobile-carrier-financial-result/ -
毎日新聞「<1分で解説>スマホ大手、続々値上げ…なぜ値下げ競争から一転?」
https://mainichi.jp/articles/20250906/k00/00m/020/119000c -
NTTドコモ「各種手続きに関わる事務手数料を改定」
https://www.docomo.ne.jp/info/news_release/2025/08/05_02.html


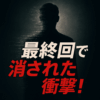


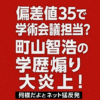

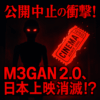



最近のコメント