【9月12日】日本の歴史で起きた代表的な出来事3選!意外な“再スタート”の日とは?
とりコレ3行まとめ
-
9月12日は「水路記念日」や「鳥取県民の日」など、制度や地域の再スタートが重なる日です。
-
明治時代の“水路局”設立は、日本の海上安全や海図作成の始まりとなった重要な出来事。
-
鳥取県の再設置は、県民アイデンティティや地方自治を考えるうえで欠かせない歴史的転換点です。
9月12日ってどんな日?意外と知られてない歴史的エピソード
「今日は何の日?」という質問に、すぐ答えられる人は少ないですよね。
実は9月12日は、日本の歴史において“再スタート”や“制度の始まり”が重なった、ちょっと特別な日なんです。
この記事では、9月12日に起きた日本の歴史的出来事を3つピックアップ。
学校で習った人もいるかもしれませんが、改めて振り返ると「今の生活にこんな影響があったのか!」と気づけるはず。

9月12日に起きた代表的な出来事とは?
① 1871年(明治4年)「水路局の設置」
1871年、明治政府の兵部省海軍部内に「水路局」が設置されました。
この水路局は、海の安全航行に欠かせない 海図の作成・水深調査・航路標識の整備 を担う組織です。
当時の日本は西洋に追いつこうと急速に近代化を進めていた時期で、外国船の航行や貿易も増加していました。そんな中、海の安全を守る制度づくりは急務でした。
この水路局こそが、現在の「海上保安庁水路部(現・海上保安庁海洋情報部)」のルーツであり、日本の海上インフラを支える出発点とも言えます。
つまり、私たちが安心してフェリーや船に乗れるのも、この日がスタートになっているのです。
② 1881年(明治14年)「鳥取県の再設置」
もう一つ大きな出来事が、1881年の 鳥取県の再設置 です。
実は鳥取県は、1876年に一度「島根県」に編入されていました。これは明治政府の 廃藩置県後の府県統廃合政策 によるもので、効率的な行政運営を目的としたものでした。
しかし、地域住民にとって「鳥取」というアイデンティティは強く、また地理的にも独立したほうが行政上のメリットが大きいと判断され、1881年9月12日に再び「鳥取県」として独立したのです。
この出来事は、単なる地図上の線引きではなく、住民の生活・教育・経済活動に直結する大事件。県の独立は、公共サービスや地元議会の仕組み、税制度にも影響を与えました。
現在でも9月12日は「鳥取県民の日」とされ、県内では記念行事や公共施設の無料開放などが行われています。まさに県民にとって誇りを確認する日です。
③ 「記念日として定着」
上記の歴史的出来事がきっかけで、9月12日は次の記念日が制定されています。
-
水路記念日:1871年の水路局設置を記念し、海の安全と海図作成の重要性を振り返る日。
-
鳥取県民の日:1881年の鳥取県再設置を記念。県民の一体感を深め、地域文化を振り返る日。
単なる「記念日」と片付けるのはもったいない話で、それぞれが日本の社会基盤を支える制度や地域の誇りにつながっています。
読者の疑問に答えるQ&A
Q1. なぜ水路局はそんなに重要だったの?
A. 海図や水深情報がないと船の運航は危険そのものです。外国との貿易が盛んになる中で、日本独自の安全基盤を整えるために必須の組織でした。
Q2. 鳥取県はなぜ一度島根に併合されたの?
A. 明治初期の府県統廃合政策の一環です。ただし住民の利便性や地域性を考えると、独立したほうが良いと判断され、再設置されました。
Q3. 今でもこの日は何かイベントがあるの?
A. 鳥取県では県民の日に合わせて文化施設の無料公開や記念イベントが開かれることがあります。水路記念日も、海洋関連施設で展示や解説が行われることがあります。
まとめ
9月12日は、意外と知られていないけれど 「再スタートの象徴」 と言える日です。
-
海の安全を守るための「水路局」ができた日
-
県民の誇りを取り戻した「鳥取県再設置」の日
-
それを記念する「水路記念日」「鳥取県民の日」
こうして見ると、ただの一日ではなく、日本の社会や地域を支える“基盤”が形になった大切な日なんです。
普段何気なく過ごしている日付も、ちょっと調べてみると歴史のターニングポイントが隠れています。ぜひカレンダーをめくるたびに、「今日はどんな日?」と探してみてください。
参考・引用記事
-
Kinendar.com「9月12日って何の日?記念日・出来事・有名人誕生日・石 …」 https://kinendar.com/anniversary/date/september/12.html
-
Yahoo!きっず「今日は何の日 – 9月12日は何の日」 https://kids.yahoo.co.jp/today/0912
-
Wikipedia「9月12日」 https://ja.wikipedia.org/wiki/9%E6%9C%8812%E6%97%A5

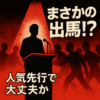
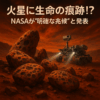



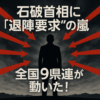
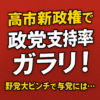




最近のコメント