【大炎上必至】シャインマスカット栽培権をNZへ!? 農水省の暴走と小泉農相に山梨県が抗議
とりコレ3行まとめ
-
農水省が「シャインマスカット」の栽培権をニュージーランドに供与検討
-
山梨県が「産地を踏みにじる暴挙」として小泉進次郎農相に抗議
-
農家からは「ブランド崩壊」「生活破壊」と批判の声が噴出
日本の宝を海外に売り渡すのか?
日本が誇る高級ブドウ「シャインマスカット」。30年近い歳月と膨大な研究費をかけて開発された品種です。皮ごと食べられ、甘さと香りが際立つ“日本農業の象徴”とも言える存在。
そんな国民的フルーツの「栽培権」を、農林水産省がニュージーランド企業に供与する方向で検討していると報じられました。
これに真っ向から反発したのが、主産地・山梨県。長崎知事が小泉進次郎農相に直談判し「農家の努力を国が裏切るのか」と強く抗議しました。
農水省は「無秩序な海外栽培を防ぐため」と説明しますが、現場農家からは「ブランド破壊につながる愚策」と非難が集中。
今回は、この問題の本質と農水省・小泉氏への批判点を整理します。

シャインマスカットと栽培権はなぜ重要なのか
ブランド価値を守る最後の砦
シャインマスカットは1980年代後半から農研機構が開発を進め、約30年の歳月を経て誕生しました。
今では高級スーパーや贈答品市場で“1房数千円”の高値をつける、まさに日本農業の成功例です。
この品種の「栽培権(ライセンス)」を他国に渡すということは、日本農業が築き上げたブランド力を自ら削る行為に等しいのです。
海外流出問題の背景
実はシャインマスカットは既に中国・韓国などで種苗が流出し、無秩序な栽培が行われています。
それらが東南アジアに輸出され、日本産と競合する事態も確認されています。
農水省は「だからこそ、正式に供与して管理下に置くべき」と主張します。ですが、管理体制が本当に機能するのか、多くの専門家や農家が疑問を抱いています。
農水省の“暴走”と小泉農相の言い訳
農水省の理屈:100億円損失の数字
農水省は「無断栽培による損失は年間100億円以上」と試算を示し、供与の正当性を訴えています。
ですが、その算定根拠は明確に公表されておらず、“数字ありきの政策”と批判されています。
小泉進次郎農相の姿勢
抗議を受けた小泉農相は「産地の理解が得られない状況では海外許諾は進めない」と回答しました。
一見、農家に寄り添う発言のようですが、裏を返せば「理解が得られれば進める」という意思を隠さない態度。
つまり、農家の不安を根本的に解消する姿勢は見られず、むしろ“言葉でごまかす”印象が拭えません。
山梨県と農家の怒り「生活を壊すな」
現場の声
山梨県は「輸出体制すら整っていない現状で、海外供与を先行させるのは理不尽」と強調。実際に、植物検疫などの壁があり、日本産シャインマスカットの輸出は進みにくい状況です。
国内農家が輸出できない間に、海外産が市場に出回れば、価格競争で日本産が淘汰されるのは目に見えています。
農家からは「自分たちの努力を国に踏みにじられた」「生活を壊すつもりか」といった怒りの声が上がっています。
「産地理解」のごまかし
小泉氏が言う「産地の理解」とは一体どこまでを意味するのか。自治体トップの合意か、農協レベルか、それとも一部団体の了承だけで進めるのか。
判断基準が不透明なままでは、「強行突破の布石では?」と疑う声が強まるのも当然です。
農水省・小泉政策の危険性
-
ブランド力低下:海外産の安価なシャインが市場に出回れば、日本産の価値は確実に下落。
-
農家の生活崩壊:価格競争で収益が減れば、産地の維持すら困難に。
-
他品種への波及:シャインが前例となり、他の国産品種も次々に“売り渡される”可能性。
-
政策の不透明性:農水省は数字を盾に急ごうとし、小泉氏はあいまいな言葉でかわす――この構図が続けば農家は守られない。
まとめ「農家を守らない農政はいらない」
今回のシャインマスカット栽培権供与問題は、単なる農業ニュースではなく、日本の農業政策のあり方を問う試金石です。
農水省は「輸出拡大」と「流出防止」を掲げますが、肝心の農家を守る視点は二の次。
小泉農相も「理解が得られなければ進めない」と言いつつ、結局は“推進ありき”の姿勢を崩していません。
30年かけて築いたブランドを、たった数年の政策判断で壊すのか。苦労して生み出した品種を簡単に海外へ渡すのは、国民に対する裏切りです。
「農家の理解」とは何か――それを曖昧にしたまま進める農政に未来はありません。今こそ国民が声を上げ、「農家を守らない農政はいらない」と突きつけるべき時です。
参考・引用記事
-
シャインマスカット栽培権、農水省がNZへ供与検討 小泉氏に山梨県抗議 — Reuters
https://jp.reuters.com/markets/commodities/A3L2SAAGXVLHBMTL6KBUMK4PAY-2025-09-25 -
シャインマスカット栽培権、農水省がNZへ供与検討 — Newsweek Japan
https://www.newsweekjapan.jp/headlines/world/2025/09/571578.php -
シャインマスカット — Wikipedia(英語版)
https://en.wikipedia.org/wiki/Shine_Muscat

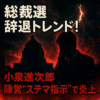
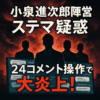
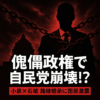
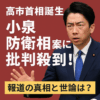

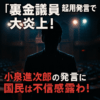




最近のコメント