【高市カラーなし批判は早計?】後藤謙次氏の“第2次麻生政権”発言に違和感
とりコレ3行まとめ
-
自民党の新役員人事をめぐり「高市カラーがない」との批判が報道された
-
ジャーナリスト後藤謙次氏が「第2次麻生政権」と皮肉発言
-
ネットでは「始まってもいないのに叩く評論家はいらない」と反発
始まる前から“批判”モード?
自民党の新しい体制が動き出そうとしている。女性初の総裁となった高市早苗氏への期待は高く、改革や新しい人材起用を望む声も大きい。
だが、まだ政策や政権運営が始まっていない段階で、早くも「高市カラーがない」「第2次麻生政権だ」と批判する論調が出ている。
特に注目されたのが、政治評論家・後藤謙次氏のコメントだ。
彼は今回の役員人事について「麻生派が全てを握った。高市の影が見えない」と断言し、「第2次麻生政権が誕生した」とまで皮肉った。
しかしネット上では、この発言に対して「叩きたいだけの評論家ではないか」「まだ始まってもいないのに決めつけはおかしい」と反論が相次いでいる。
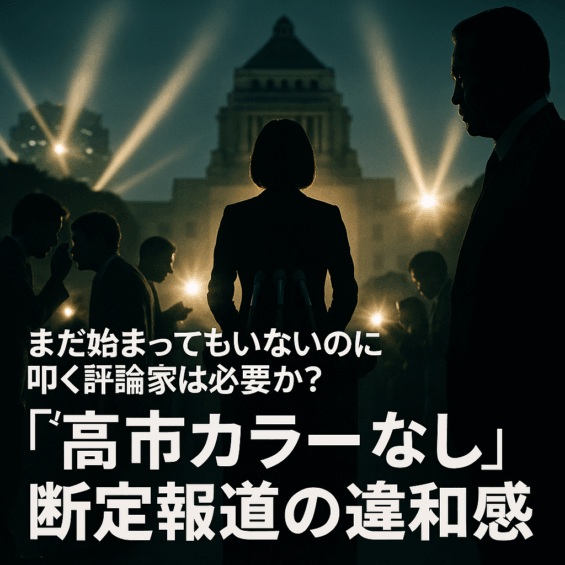
“高市カラーなし”とされた人事の中身
麻生派・旧茂木派の存在感
報道によれば、新たな自民党の役員人事や閣僚候補には、麻生派や旧茂木派の顔ぶれが目立つとされる。
幹事長に鈴木俊一氏(麻生派)、総務会長に有村治子氏(麻生派)、さらに木原稔氏や茂木敏充氏らも要職候補に挙がっている。
確かに、この人事だけを見れば「派閥の影響が色濃い」との印象を持つ人は少なくない。後藤氏が「麻生さんが全てを仕切った」と評した背景もここにある。
ただし“まだ動いていない”という事実
一方で、この段階ではまだ新内閣の政策や人事運営がスタートしていない。人事は流動的で、今後の運営や追加人事で「高市らしさ」が表に出る可能性もある。
それにもかかわらず「カラーなし」と断定してしまうのは、やや拙速な論調と言える。
後藤謙次氏の“断定批判”にネットで違和感
叩きたいだけ?評論家不要論
SNSや掲示板では、次のような意見が広がっている。
-
「政策が始まる前から“色がない”と決めつけるのはただの揚げ足取り」
-
「評論家は批判するために存在しているのか?」
-
「国民が見たいのは未来に向けた政策であって、評論家の皮肉じゃない」
こうした声からも分かるように、“まだ何も始まっていない段階での断定的批判”は、メディアや評論家の信用を下げる結果につながっている。
メディア不信を加速させる危険性
長年政治を取材してきた後藤氏の言葉は影響力が大きい。
しかし、その発言が「叩くための材料」にしか見えないとなれば、若い世代を中心に「またオールドメディアか」と白けた反応を生む。
実際に、10代〜30代の世代はテレビや新聞よりネット情報に触れる時間が圧倒的に多い。だからこそ、断定的な批判は逆効果になりやすいのだ。
“高市カラー”はこれから見えてくる
真に注目すべきポイント
政治における“カラー”とは、単なる人事配置だけで決まるものではない。
-
予算配分の優先順位
-
新しい政策の打ち出し方
-
若手や女性の登用
-
与野党との交渉姿勢
これらが具体的に示されて初めて「高市カラー」が見える。
人事だけで決めつけるのは早計であり、むしろ今後の政権運営を見極めることが重要になる。
批判より“チェック”が必要
評論家やメディアに求められるのは、皮肉や決めつけではなく、政権の動きを冷静にチェックし、問題点を的確に指摘する役割だ。
ただ叩くだけでは建設的な議論にはつながらない。国民が求めているのは「何が問題で、どう改善できるのか」という解説であり、皮肉ではない。
読者が抱える素朴な疑問
Q. そもそも“高市カラー”って何?
→ 高市氏が総裁選で掲げたビジョンや政策方針、女性初の総裁としての新しさが反映されることを指す。
Q. なぜメディア批判が強いの?
→ 政策が動き出す前から「失敗」「影がない」と決めつける報道が多いため、視聴者が“印象操作”だと感じやすいから。
Q. 本当に“麻生政権”になる可能性は?
→ 麻生派の影響が大きいのは事実だが、最終的には総裁=高市氏の判断次第。政策や内閣の動向を見て判断するしかない。
まとめ|必要なのは“皮肉”ではなく“冷静な視点”
今回の自民党人事をめぐる報道では、評論家の後藤謙次氏が「高市カラーなし」と断言し「第2次麻生政権」と皮肉ったことが注目を集めた。
だが、まだ政権運営が始まっていない中での“断定批判”は、ただ叩きたいだけに見え、若い世代を中心に強い違和感を呼んでいる。
これから本当に重要なのは、人事よりも政策、そして実際の運営で“高市カラー”がどう表れるかだ。評論家やメディアには、皮肉よりも冷静な視点と建設的な分析が求められている。
参考・引用記事
-
後藤謙次氏 高市カラーなしの自民党役員人事に皮肉「第2次麻生政権が誕生した」
https://www.sponichi.co.jp/society/news/2025/10/06/kiji/20251006s00042000264000c.html -
後藤謙次氏が指摘 高市体制の党役員&閣僚候補に“衝撃”共通点
https://www.sponichi.co.jp/society/news/2025/10/06/kiji/20251006s00042000270000c.html -
永田町ライヴ!(後藤謙次コラム紹介)
https://diamond.jp/list/feature/p-nagatacholive

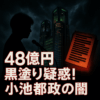
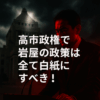
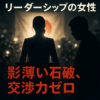
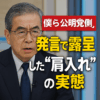

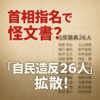
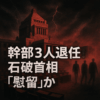




最近のコメント