【緊急解説】能登半島地震「古いマグマ破壊」が大規模化のカギ?東北大が示した地下の真相
とりコレ3行まとめ
-
東北大の研究で、震源近くの「固まった古いマグマ(硬い岩塊)」が壊れたことが、大規模地震につながった可能性が浮上。
-
群発地震が続いた隣で“限界突破”が起き、断層破壊が一気に広がったとみられる。
-
今後の地震予測では、地下構造と地殻応力を組み合わせた監視が重要になる。
能登半島地震
2024年1月1日に発生した能登半島地震(Mw7.5/Mj7.6)。津波、地盤隆起、家屋倒壊などを引き起こした“元日直撃”の大災害です。
その地震の裏で「古いマグマの塊」が決定的な役割を果たしていたことを、東北大学の研究チームが明らかにしました。
固まったマグマは普段“ブレーキ”になる存在ですが、限界を超えた瞬間に“スイッチ”のように破断を広げたのです。
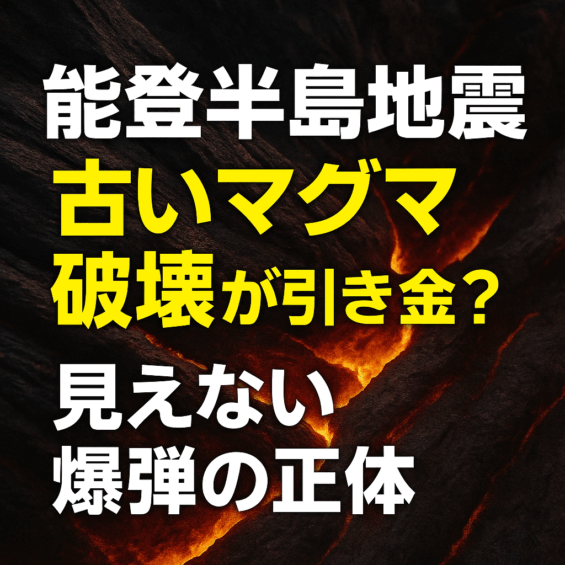
能登半島地震で何が起きたのか?
-
群発地震から本震へ
2020年末ごろから群発地震が続き、2024年元日に大地震が発生。断層破壊は東西に広がり、津波や最大4メートルの地盤隆起も発生。 -
被害規模
死者は500人超、建物被害18万件以上。経済的損失はおよそ100億ドル規模と推定。 -
従来の理解
群発地震の要因は「地殻流体の上昇」や「古い断層の再活動」とされてきました。
東北大が示した「古いマグマ破壊」のシナリオ
-
震源の地下に眠っていた硬い塊
地下5〜15kmに存在する幅10〜15kmの硬い岩塊。これが「固まった古いマグマ」と考えられています。 -
ブレーキから引き金へ
この塊は普段、断層の動きを抑える役割をしていました。しかし歪みが限界に達し、ついに破壊。断層破壊が一気に広がり、大地震を大規模化させたと解釈されています。 -
科学誌に掲載
この成果は米科学誌「Science Advances」に掲載。群発地震から本震への流れを説明する新しいカギになっています。
古いマグマが地震を大きくした理由
硬い岩塊は「二面性」を持つ
硬い塊は普段は地震を抑える“壁”ですが、限界に達すると“連鎖破壊の起点”に。今回はその転換が起き、大規模破壊につながったと考えられます。
群発地震との関係
能登の群発地震は、地下からの流体が原因とされていました。その活動が硬い塊に影響を与え、限界を突破させた可能性が高いのです。
「すべりやすい断層」が揃っていた
別の研究では、能登の断層が“すべりやすい状態”にあったことも示されています。硬い塊+断層の状態、二つの条件が重なって大地震につながったのです。
私たちにどう関係するのか?
-
群発地震はサインかも
長期にわたる群発地震は、地下構造によっては大地震に直結する可能性があります。 -
景色が変わるほどの影響
能登では海岸線が一気に前進。地震は“景色そのもの”を変えてしまう力を持っています。 -
次への備え
家具の固定、避難袋の準備、ハザードマップの確認。加えて、研究成果を元にした「危険度マップのアップデート」にも注目したいところです。
まとめ
能登半島地震は、単なる断層活動では説明しきれない現象でした。
東北大学の研究は「固まった古いマグマの破壊」という新しい視点を示し、群発から本震への流れをより鮮明に描き出しました。
私たちが知るべきは「群発地震+地下構造のクセ」で、これが次の大きな地震を引き起こすサインになるかもしれないということ。
科学の進展は減災のためのヒント。備えを重ねつつ、最新研究の動きに注目していきましょう。
参考・引用記事
-
Rupture of solidified ancient magma that impeded faulting ultimately led to the 2024 Noto Peninsula earthquake(Science Advances)
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adv5938 -
古いマグマが大規模化要因 能登地震、東北大解析(沖縄タイムス=共同)
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1692486 -
古いマグマが大規模化要因 能登地震、東北大解析(福島民友=共同)
https://www.minyu-net.com/newspack/detail/2025101501002228 -
2024年能登半島地震の断層活動を地殻応力場で推定(東北大学・プレス)
https://www.aob.gp.tohoku.ac.jp/finding/press/press-2025/ -
Shoreline advance due to the 2024 Noto Peninsula earthquake(Scientific Reports)
https://www.nature.com/articles/s41598-024-79044-4 -
The 2024 Noto Peninsula Earthquake(Gallagher Re レポート)
https://www.ajg.com/gallagherre/-/media/files/gallagher/gallagherre/news-and-insights/2025/may/gallagherre-the-2024-noto-peninsula-earthquake.pdf -
地殻流体によって誘発された能登半島の群発地震(東京工業大学プレス, 2022/11/4)
https://www.titech.ac.jp/news/pdf/tokyotechpr20221104-nakajima.pdf

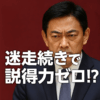
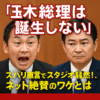
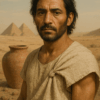
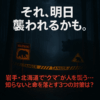
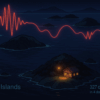

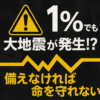




最近のコメント