【超発見】古代バビロンの“賛歌”がAIで復元!3000年前の学校テキストだった!?
とりコレ3行まとめ
-
3000年前のバビロンで使われた詩がAIの力で解読
-
粘土板30枚以上から復元、約250行の2/3を再構築!
-
子どもたちが学校で書き写していた「古代の教科書」だった証拠も!
3000年前の“教科書”が現代に!教育のルーツが見えてきた
現代の学校にも通じるような“写し書き”の文化が、なんと古代バビロンにもあった――そんな驚きの発見が話題になっています。
イラクとドイツの研究チームが、AIを使って粘土板に刻まれた詩「バビロンの賛歌」を復元。
その内容だけでなく、当時の教育の様子まで明らかになってきました。この記事では、復元された内容のスゴさと、学校での活用方法まで詳しくご紹介します!
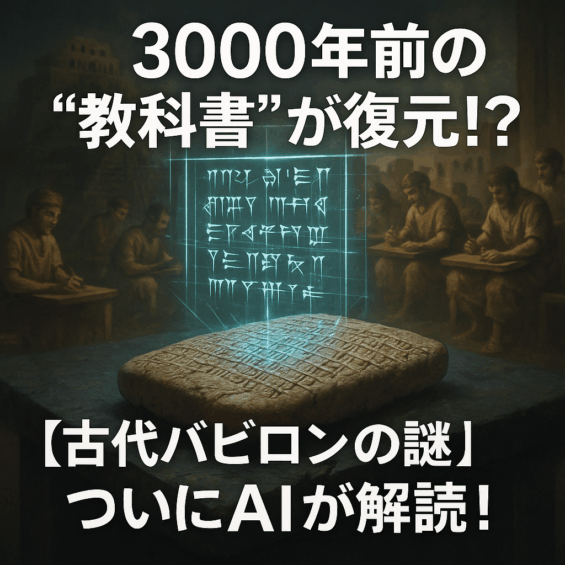
発見された“バビロンの賛歌”ってどんなもの?
今回の発見は、イラク・バグダッド大学とドイツ・ミュンヘン大学の研究者たちによるプロジェクトの成果です。
対象となったのは、紀元前13世紀〜1世紀頃まで写本されていた「バビロン賛歌」という詩。
この詩は、当時の都市バビロンや守護神マルドゥクを称える内容で、社会秩序や自然への賛美、さらには神殿で働く巫女の役割や異邦人への寛容さなども記されています。
もともと粘土板に刻まれた楔形文字で記録されていたため解読には長年かかるとされていましたが、AIによるパターン認識技術を使うことで粘土板30枚以上の断片を組み合わせ、全体約250行のうち2/3を復元することに成功しました。
学校教育にも使われていた!その証拠とは?
さらに驚くべきなのは、この詩が単なる宗教的な賛歌ではなく、教育現場でも活用されていたという事実です。
考古学的には「eduba(エドゥバ)」と呼ばれる古代メソポタミアの“写字学校”で、子どもたちがこの賛歌を写本する課題として取り組んでいた形跡が発見されました。
実際に、20〜30枚もの粘土板に同じ賛歌の文面が繰り返し書かれていたことから、教師と生徒による模範と練習のやり取りであった可能性が高いと見られています。
今で言う“書き取りの授業”が3000年前に行われていたとは…ちょっと衝撃的ですね。
古代の子どもたちが学んでいた内容とは?
詩の中には次のような描写があります。
「ユーフラテス川が彼女の川となり、緑の麦を育て…」
「都市は公平を守り、異邦人にも扉を開く…」
自然の恵み、都市の平和、社会の調和など、現代にも通じる価値観がしっかりと詠まれています。そして、そういった価値を子どもたちが日々の授業で学んでいたということが分かります。
神々の名前を覚えるだけではなく、「社会をどう見るか」という視点を育てる教材でもあったというのが興味深いポイントです。
そもそもどうやって解読したの?AIの活躍がすごい
粘土板は長年バラバラの状態で保管されており、手作業での再構成は非常に困難でした。
今回の研究チームは、AIが文のパターンを自動で分析・照合するプラットフォームを使用。30枚以上の写本断片を突き合わせ、同じ詩が何度も記録されていたことをAIが特定しました。
これにより、断片の位置づけが一気に明確になり、数十年かかるとされた研究が数ヶ月で進んだということです。
AIの活用で、古代文字の解読スピードが飛躍的に上がる時代が本格的に始まったとも言えます。
まとめ:古代のロマンと、教育の原点に触れる発見
-
約3000年前のバビロンで詠まれた賛歌がAIで復元
-
子どもたちが“教科書”として書き写していた痕跡あり
-
都市の理想像や自然への感謝、寛容性を学ぶ教材だった
-
AIの技術で数十年分の研究が加速中!
人間の価値観って、実は昔からあまり変わってないのかも――そんな気づきをくれる今回の発見。

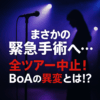
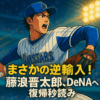
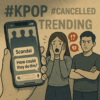
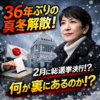
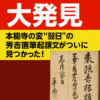
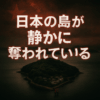
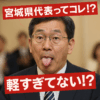




最近のコメント