【閉鎖ショック】日産・追浜工場が2028年に車両生産終了へ!約3900人に影響…街全体が揺れるその全貌
◆とりこれ3行まとめ
-
日産が神奈川県・追浜工場の車両生産を2028年3月に終了すると正式発表
-
約3900人が影響を受け、地域の雇用や住宅市場にも深刻な影響が広がる可能性大
-
EV戦略とコスト削減を背景にした大規模再編、その波紋は全国に広がるかも?
◆全国に波及する可能性も?日産追浜工場閉鎖のインパクトとは
2025年7月、日産自動車は「追浜(おっぱま)工場での車両生産を2028年3月末で終了する」と発表しました。
このニュースは地元・神奈川県横須賀市を中心に大きな反響を呼んでいます。
追浜工場といえば、1961年に稼働を開始し、60年以上にわたり日産の主力製造拠点として機能してきた場所。ハイブリッド技術「e-POWER」を搭載した車両の先進的な生産ラインもあり、技術力の象徴でもありました。
今回の閉鎖は日産の“再生計画”の一環ですが、それにより発生する現実的な影響は想像以上に広範囲。
特に30代〜40代の家庭持ち社員にとっては、「住宅ローン」「子育て」「通勤の再設計」など、生活基盤そのものに関わる問題です。
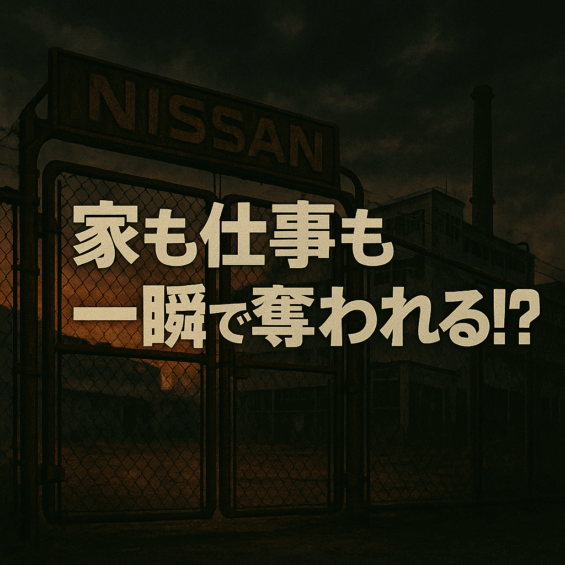
◆追浜工場とは?日産の“心臓部”だった製造拠点
-
所在地:神奈川県横須賀市夏島町
-
稼働開始:1961年
-
生産車種:ノート、オーラなどの小型車(ハイブリッド含む)
-
主な役割:先進運転支援技術やEV関連試験なども兼ねる拠点
また、追浜には試験走行用のテストコースや専用港湾施設もあり、単なる“工場”という枠を超えた日産の技術と物流のハブでもありました。
これが車両生産から撤退するというのは、企業体質を根本から見直すレベルの大改革と言えます。
◆閉鎖の背景にある“日産の本音”とは?
今回の決定には、大きく分けて3つの背景があります。
1. 生産体制の効率化
世界中の工場を「17拠点 → 10拠点」へと集約する方針が進行中。これにより、管理コストや人件費を削減し、利益率の改善を狙っています。
2. グローバル競争の激化
トヨタやテスラといった競合企業が急速にEV(電気自動車)シフトを進める中、日産も追従する形で生産拠点の見直しを急いでいます。
3. 財務の立て直し
2024年度決算では約6700億円規模の最終赤字を計上。財務の健全化には思い切った構造改革が必要だったと見られています。
◆「家を買ったばかりなんだけど…」広がる生活不安
今回の閉鎖報道により、最も強く動揺しているのは、地元の従業員とその家族たちです。
「子どもを地元の小学校に通わせてる」
「数年前に住宅ローンを組んだばかり」
「夫婦共に日産勤務で、同時に職を失うかも」
こうしたリアルな声がSNSや地元紙などで噴出しています。
さらに、追浜工場に依存していた飲食店や保育施設、不動産会社など“関連業界”にも連鎖的な影響が及んでいます。
すでに建設予定だった近隣のタワーマンションが着工延期になるなど、街全体に暗い影を落とし始めています。
◆フォックスコンとの連携報道は“希望の光”か?
一部報道では、台湾の大手企業フォックスコン(鴻海精密工業)と日産が、追浜工場を活用してEV生産の提携を模索しているとの情報も出ました。
ただし、現時点で日産は正式な契約や決定事項は発表しておらず、あくまで「交渉段階」と見られます。
仮に実現すれば、生産ラインの維持や雇用の一部救済が期待できますが、確定ではないため、過度な期待は禁物です。
◆今、必要な“備え”とは?生活防衛の具体策まとめ
突然の雇用リスクに直面したとき、私たちにできることは意外と多くあります。
✅ 失業保険や職業訓練の利用
ハローワークや労働局で提供されている職業訓練制度は、再就職への第一歩。自治体の相談窓口を活用するのも有効です。
✅ 住宅ローンの見直し
金融機関によっては、「支払い猶予」「返済期間の延長」「条件変更」が可能なケースも。まずは借入先に相談を。
✅ 資産運用や副収入の確保
今こそ「会社に頼らない収入源」を作るタイミング。副業やスキルアップにチャレンジする人も増えています。
◆まとめ:大きな変化の中で「生き残る力」を考えよう
日産・追浜工場の車両生産終了は、企業の一手というより、働き方・暮らし方そのものに警鐘を鳴らす出来事です。
企業の都合で人生が左右される時代だからこそ、情報を得て備える力、そして柔軟に動ける行動力が求められています。
「もしかしたら自分の会社も…」と感じたあなた。この出来事を“他人事”にしないことが、これからのサバイバル力につながります。

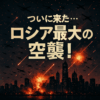
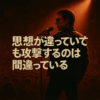
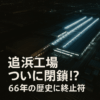

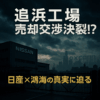






最近のコメント