【大量閉店】高級食パンに何が!?【銀座に志かわ】90店閉店の裏側とは
とりコレ3行まとめ
-
一時は全国に140店舗以上を展開した「銀座に志かわ」が、現在は約50店舗まで激減!
-
高級食パンブームの終焉、価格への疑問、そして経営戦略の見直しが閉店ラッシュの背景に
-
社長が語った“失敗の本質”から、今後の飲食ビジネスのあり方が見えてくる
一世を風靡した“1000円の食パン”が急減!何が起きた?
「1本864円(税込み)」という強気の価格設定にもかかわらず、連日完売を記録した高級食パン専門店「銀座に志かわ」。
水にこだわり、耳まで柔らかい“甘いパン”としてSNSやメディアで話題になり、2018年の創業からわずか数年で全国に140店舗を超えるまでに拡大しました。
そんな「銀座に志かわ」が、現在はなんと約50店舗にまで縮小しているという事実、ご存じでしたか?
今回は「なぜ急に閉店ラッシュが起きたのか?」という疑問をもとに、ブームの光と影、そして社長自らが語った“敗因”まで掘り下げてご紹介します。
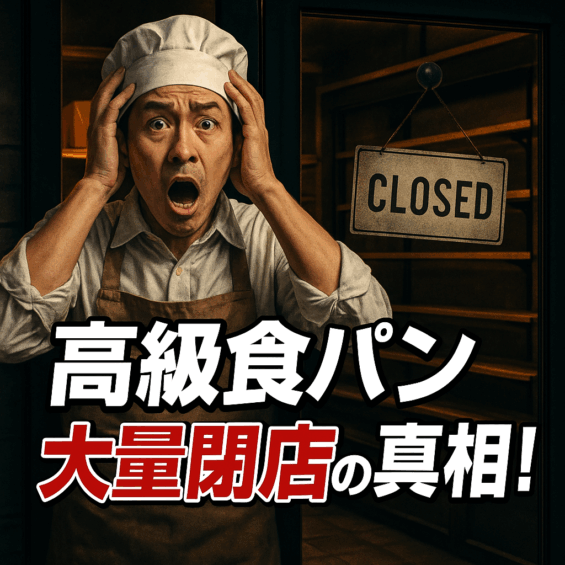
銀座に志かわとは?~高級食パンブームの象徴~
「銀座に志かわ」は2018年に東京・銀座で1号店をオープン。
特徴的なのは、アルカリイオン水を使った独自の製法で、ふわふわで甘みのある食パン。耳まで柔らかく、そのまま食べても、ワインやチーズとも相性が良いと話題になりました。
一時は「食パン界のエルメス」「1本1000円でも売れるパン」とも称され、特に30〜50代の女性を中心に大ヒット。
高級感ある店舗設計や、手土産文化にマッチしたパッケージも受け、まさに“インスタ映えグルメ”としても爆発的に流行しました。
しかし、そんな人気にも陰りが…。
なぜ90店舗も閉店?急落の3つの理由
ここからは、「銀座に志かわ」が大量閉店に至った背景を大きく3つに分けて解説します。
① 食パンブームの終焉
2019年~2020年にかけて訪れた“高級食パンブーム”。コロナ禍での内食需要も後押しし、各社がこぞって参入しましたが、流行には必ず終わりがあります。
多くの人が“話題性”で一度は購入したものの、「リピートするには高すぎる」「毎日は食べられない」といった声が増加。ブームの終息とともに集客力も低下しました。
② 競合の増加と差別化の難しさ
「乃が美」「嵜本」などのライバル店が全国に急増。各社が似たコンセプトの商品を出す中で、「高級食パン」というジャンル自体がコモディティ化(差別化できない商品化)してしまいました。
消費者からすると「どれも似てる」と思われるようになり、結果的に価格勝負になっていきました。
③ 原材料費の高騰
小麦、バター、砂糖など主原料の価格は年々上昇。ウクライナ情勢や円安の影響もあり、仕入れコストが跳ね上がった中でも、銀座に志かわの価格は据え置き。
利益が出にくくなり、特にフランチャイズ店の経営が厳しくなっていきました。
社長が語る“反省点”と今後の戦略
今回の閉店劇について、「銀座に志かわ」代表・田島慎也社長はインタビューで率直に“敗因”を語っています。
最大の反省点は「急拡大によるフランチャイズ依存」です。店舗展開を急ぎすぎたことで、立地やオーナーの力量にバラつきが出て、結果的にブランド力が維持できなかったと分析。売れる場所・売れる人に依存していたことが、ブーム後の耐性の無さにつながったとしています。
今後は「地域密着型」へのシフトが課題とのこと。無理に全国展開するのではなく、1店舗1店舗が“地元の定番”になれるよう、商品や販売スタイルも柔軟に見直していく方向性を示しています。
ブームで終わらせない!持続するブランドの鍵とは?
今回の「銀座に志かわ」の例は、飲食・小売業に共通する教訓を与えてくれます。
短期的に話題を集めても、継続的に売れ続ける商品やブランドにするには、「リピートされる仕組み」が不可欠。
価格と品質のバランス、日常使いへの転換、地域とのつながり——これらが今の消費者には求められています。
「また買いたい」「近所にあって助かる」と思ってもらえることが、長期的なブランド存続の鍵と言えるでしょう。
まとめ
銀座に志かわの大量閉店は、一過性のブームに頼ったビジネスモデルの“終焉”を象徴しています。
華やかな人気の裏で見落とされがちな「地に足のついた運営」が、今後ますます重要になっていくはずです。
今後の再起に期待しつつ、「自分のビジネスはどうだろう?」と振り返る良いきっかけにしてみてくださいね。

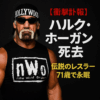
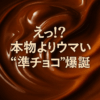


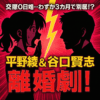






最近のコメント