【驚き実話】妻との性交で知った無精子症 SNS精子提供で訴える男性の叫び
とりコレ3行まとめ
-
妻の妊活をきっかけに、自身の無精子症が判明した男性が話題に。
-
その後SNSで精子提供活動を始めるも、現場には法整備の遅れやトラブルの影が。
-
当事者たちは「国が早急に制度を整えるべき」と声を上げている。
「SNSで精子提供」という現実
2025年、SNSを介した精子提供の話題が再び注目を集めています。
発端は、友人の依頼で性交渉を通じて精子提供を試みた男性が、検査をきっかけに自身が無精子症であることを知ったという衝撃の出来事。
驚くのは、彼だけではありません。日本では、生殖補助医療の選択肢が限られているため、多くの人がSNSを通じて精子提供を探す現状があります。しかし、この流れには危険も潜んでいます。
今回の事例は、精子提供の現場がいかに制度面で未整備であり、リスクを抱えているかを改めて浮き彫りにしました。

生殖補助医療の現状と背景
無精子症と日本の医療制度
無精子症とは、精液中に精子が全く存在しない状態を指します。
妊娠を望む男性にとって大きな衝撃となる診断ですが、治療は可能な場合もあれば、根本的な解決が難しいケースもあります。
日本の生殖補助医療では、医療機関を通じたAID(非配偶者間人工授精)が行われていますが、対象は基本的に法律婚をしている異性カップルに限定されています。
そのため、無精子症と診断された男性や、未婚・同性カップル・シングルマザーなど、制度の枠外にいる人々は、公的なサポートがほとんどないのが現実です。
結果として、医療機関外での方法、特にSNSを介した個人間の精子提供に頼るケースが増えているのです。
SNSで広がる精子提供、その実態
個人間で行われる精子提供とトラブル
SNSでは、匿名アカウントを使って「精子提供者」を名乗る男性が活動し、容姿や学歴、健康状態などを“ウリ”として情報発信しています。
しかし、こうした提供活動は法的な裏付けがない状態で行われており、依頼者と提供者の間でトラブルが起きる事例も多発しています。
たとえば、提供者が実際には性交渉による提供を条件としていたり、プロフィールの学歴や国籍が虚偽だったりするケースが報道されています。
また、感染症や遺伝性疾患の検査が不十分なまま提供が行われることもあり、健康リスクが伴います。
さらに、2021年にはSNSで知り合った女性に提供を行った男性が、情報の虚偽や精神的苦痛を理由に訴えられる事件も発生しています。こうした事例は氷山の一角に過ぎず、安全性や信頼性に大きな不安があるのが現実です。
疑問&解決ポイント
精子提供は安全なのか?
結論から言えば、医療機関を通さない提供は安全性が保証されていません。
SNS提供では、提供者がどれだけ「健康診断済み」とアピールしても、実際には最新の検査結果を提示しない場合や、必要な検査項目が抜けているケースが多くあります。
感染症(HIV、梅毒、B型肝炎など)のリスクや、遺伝性疾患を見落とす危険性もあります。
また、提供者との間で法的な契約がないため、トラブル発生時の責任追及が困難です。
法整備はどうなっている?
日本では現在、「特定生殖補助医療法案」が国会で議論されています。
この法案では、精子提供によって生まれた子どもが出自を知る権利を持てるよう、一定範囲でドナー情報を開示する仕組みが盛り込まれています。
しかし現状では、
-
対象は法律婚をしている異性カップルのみ
-
ドナー情報は制限付きで、名前や連絡先は本人の同意がない限り非公開
-
同性カップルや未婚女性への提供は対象外
こうした制限が多く、当事者や支援団体からは「制度が現実に追いついていない」と批判の声も上がっています。
まとめ:SNS提供は“最後の手段”?制度の整備が急務
今回の男性のケースは、無精子症という個人の事情から始まりましたが、背景には制度不足によってSNSに頼らざるを得ない社会構造があります。
-
無精子症を知るきっかけは人それぞれだが、情報や支援はまだ不足
-
SNSを介した精子提供は、安全性・法的リスク・トラブルの危険が高い
-
制度の整備が遅れるほど、同様のケースは増え続ける可能性がある
国がしっかりと制度を整え、安心して妊活できる環境を作ることが、今後の課題です。

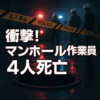
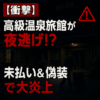
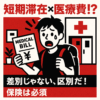
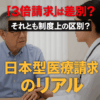


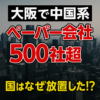




最近のコメント