【米ショックはまだ続く?】新米5kg“7,800円”報道の衝撃!農家は苦しいのに中間業者だけ得してる⁉
とりコレ3行まとめ
-
2025年、新米価格が急騰。地域によっては5kg 7,800円という異常事態も!
-
でも農家は原料費や燃料費の高騰で“儲かっていない”という声が続出。
-
実際に潤っているのは中間業者や流通の仕組み…このままでは日本のお米がピンチ!
なぜお米がここまで高くなったのか?
「お米が高すぎて、もう高級食材じゃん!」
そんな声がSNSで広がっています。2025年の新米シーズン、日本中で“米ショック”が起きています。
通常、スーパーで売られる5kgの新米は3,000〜4,000円程度が相場でした。
しかし今年は一部地域で5,000円超え、さらに報道によっては7,800円という例も紹介されました。まさに“異常価格”。
ただしここで大事なのは、「農家がウハウハ」というわけでは全くないこと。実際には、農家は燃料や肥料の高騰で苦しみ、「このままでは赤字かも」と嘆いています。
ではなぜこんなに価格が上がり、農家が報われない構造になっているのか。その背景を掘り下げます。

新米高騰の5つの原因
まずは、新米が高騰した要因を整理しましょう。単純に「不作だから高い」という話ではなく、複数の要因が複雑に絡んでいます。
1. 異常気象の影響
2025年の夏は全国的に猛暑。気温が高すぎると米粒が白く濁る「白未熟粒」が増え、出荷できる“良質米”の割合が減少しました。
結果的に市場に出る新米が減り、価格が急上昇。
2. 農業コストの爆上がり
肥料は輸入依存。ウクライナ情勢や円安の影響で、価格が2倍以上になった例もあります。加えて燃料代や電気代も上昇。
米価が上がっても、農家の経費がさらに上がっているため、利益はほとんど残りません。
3. 農家の減少と後継ぎ不足
日本の農業は高齢化が深刻で、後継者不足も顕著。田んぼをやめる農家が増えていて、全体の生産量が落ちています。
供給が減れば価格が上がるのは当然です。
4. 在庫不足
ここ数年の減反政策や需要回復の影響で、政府やJAが持つ備蓄米も減っています。
在庫が少ないため、価格を抑える力が働きにくい状態です。
5. 備蓄米の限界
政府は実際に備蓄米を市場に放出しました(21〜23万トン規模)。
しかし古米が多く、家庭用のスーパーにはほとんど出回りませんでした。そのため消費者は「高い新米」しか選べない状況に。
② 農家は儲かってるの?現場のリアル
「米が高いなら農家は儲かるでしょ?」と考える人も多いですが、実情は真逆です。
たしかに今年はJAの“概算金”(農家に払われる仮の買い取り価格)が前年より5〜8割も高くなった地域もあります。
中には「ようやく農業が黒字になりそう」という農家の声もありました。
でもその裏で、こんな声が続出しています。
-
「肥料代と機械の維持費で帳消し」
-
「赤字にはならないけど、生活は楽じゃない」
-
「米価は上がっても、農業を続けるモチベは上がらない」
つまり“数字上は改善”していても、農家が豊かになったとは言い切れないのです。
③ 中間業者だけが儲かるワケ
問題はここから。店頭価格が急上昇しているのに、農家に利益が回っていないのはなぜか?
仕組みのカラクリ
-
農家はJAに米を出荷
-
JAや卸売業者が買い取り、小売店へ販売
-
その過程でマージン(利益)が積み重なる
つまり、消費者が7,000円で買った米でも、農家に入るのはその一部だけ。中間の流通で利益がどんどん抜かれているのです。
減反政策と在庫調整
さらにJAや大手業者は、在庫をコントロールすることで価格を維持。供給を絞れば高値が続き、中間で儲けられる構造になっています。
この仕組みが続けば、「消費者は高い米を買わされる」「農家は報われない」という最悪の状態が固定化されます。
④ 今後どうなる?価格は下がるのか
実は2025年の夏以降、価格は少し落ち着きつつあります。6月末時点では5kgで4,000円弱、7〜8月には3,000円台に落ち着くとの見通しも出ています。
理由は、政府が備蓄米を大量に放出したこと、さらに輸入米(アメリカ・ベトナム・台湾など)の受け入れが進んだため。これにより「一時的なパニック価格」は下がり始めています。
ただし、これは短期的な緩和。根本的に農家が報われない構造が変わらなければ、また同じことが繰り返されます。
⑤ まとめ:お米を守るのは消費者の選択もカギ
今回の“米ショック”は、単なる天候不順や世界情勢だけが原因ではありません。日本の農業構造そのものが抱える問題が表面化したとも言えます。
-
農家に直接お金が届く仕組みが必要
-
消費者も「安ければいい」ではなく選び方を変える必要がある
-
ふるさと納税や直販サイトで農家を応援するのも効果的
未来のお米を守るためには、農家が続けられる環境づくりが欠かせません。
「高いのは仕方ない」ではなく、「高いのに農家が報われない」ことこそ問題。そこを見抜くことが、私たち消費者にできる第一歩です。
参考・引用記事一覧
-
「新米売って」高値持ちかける業者、それでも…米農家が見据える危機(朝日新聞) https://www.asahi.com/articles/AST784Q0DT78UOHB003M.html
-
JA農協&農水省がいる限り「お米の値段」はどんどん上がる…(PRESIDENT Online/CIGS) https://cigs.canon/article/20241008_8369.html
-
【2025年版】なぜ米の値段が高騰しているのか?(note) https://note.com/shuji0075/n/n67702009dea6
-
日本の米価格の高騰の背景(Arab News日本版) https://www.arabnews.jp/article/business/article_151092/
-
Emergency reserves, high prices, rationing. How did Japan’s rice crisis get this far?(AP News) https://apnews.com/article/6e21bc9017c8f6d8c0a1f179e50e975f
-
Soaring prices, empty shelves as Japan’s rice crisis worsens(Washington Post) https://www.washingtonpost.com/world/2025/04/26/japan-rice-shortage-imports/
-
Against the grain: as prices and temperatures rise, can Japan learn to love imported rice?(The Guardian) https://www.theguardian.com/world/2025/jun/11/against-the-grain-as-prices-and-temperatures-rise-can-japan-learn-to-love-imported-rice

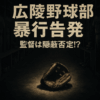
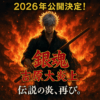
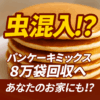

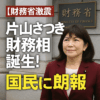

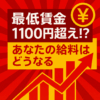




最近のコメント