【無責任】教育委員会の8割がする防犯カメラを拒む言い訳とは?
3行まとめ
-
教育委員会の8割以上が「防犯カメラ設置を検討していない」と判明
-
教員による性暴力やいじめ問題が続く今こそ“守る仕組み”が必要
-
カメラは子どもだけでなく、教員自身を守る盾にもなる
いま本当に“いいの?” 教育委員会の対応
近年、全国で教員によるわいせつ事件や体罰、いじめの見逃しが相次いでいます。
そんな中で注目されているのが「教室への防犯カメラ設置」。
しかし、2025年7月の毎日新聞の調査によると、全国の教育委員会のうち 84%が「検討していない」と回答。
「検討している」はわずか5機関で、「前向きに進める」という姿勢はほとんど見られませんでした。
これは子どもを守る責任を持つ教育現場として、本当に正しい対応といえるのでしょうか?
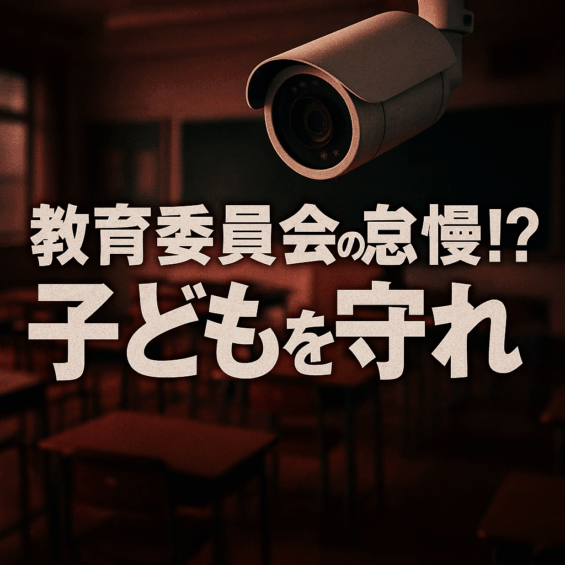
教育委員会が動かない“言い訳”とは?
教育委員会がカメラ設置をためらう理由は大きく3つあります。
-
プライバシーの懸念
「教室は学びと交流の場。録画されれば自由な発言や行動が萎縮する」という声があります。 -
教育環境の悪化を心配
監視カメラが“監視社会”を連想させることで、子どもや教師の心理に悪影響を与えるのではないかという懸念。 -
コストや運用ルールの難しさ
設置費用だけでなく、「誰が映像を見るのか」「どれくらい保存するのか」など運用ルールの整備が負担になるという指摘。
こうした課題は確かに存在します。しかし、それを理由に 「議論すらしない」という姿勢は怠慢 と言わざるを得ません。
それでもカメラを義務化すべき理由
では、なぜカメラ設置が必要なのでしょうか?
1. 性暴力・いじめの強力な抑止力になる
カメラがあることで「不正行為をすれば記録される」という意識が働き、性暴力や体罰、いじめの抑止効果が期待できます。
2. 証拠として機能する
万が一事件が起きた場合、被害者の声だけではなく「客観的な映像」が残ることは、裁判や処分において決定的な意味を持ちます。
3. 教員自身も守れる
カメラは「加害を防ぐ」だけでなく、教員が濡れ衣を着せられたときにも自分を守る盾になります。子どもを守ると同時に、まっとうに働く先生を守ることにもつながります。
4. 部分的設置やルール化で課題は解決できる
プライバシーの懸念は、教室全体ではなく「入り口のみ録画」や「一定期間で自動削除」など、運用次第で解消可能です。
5. 国の制度改正とセットで強化できる
2026年12月には「こども性暴力防止法」が施行され、日本版DBS(性犯罪歴の確認制度)も導入予定です。ソフト面の対策に加え、ハードとしてのカメラ設置を進めれば、より強固な安全網が完成します。
子どもを守る社会のために必要なこと
これからの教育現場には「プライバシーを守りつつ、安全を最大化する知恵」が求められています。
-
ルールの透明化:録画データは「事件発生時のみ閲覧」「一定期間で自動削除」などを徹底
-
柔軟な設置方法:トイレや更衣室は除外、入り口だけを録画などケースごとの工夫
-
制度との連携:DBS制度や研修制度と併せて総合的に運用
こうした工夫をすれば「監視社会になる」という批判をかわしつつ、子どもの命を守る環境を整えることができます。
まとめ
教育委員会の8割が「検討すらしない」姿勢を続けるのは、子どもを守る責任の放棄です。
防犯カメラは完璧な解決策ではないものの、いじめや性暴力を減らすための有効な手段であることは明らかです。
「やらない理由」を探すのではなく、「どうやれば実現できるか」を真剣に考える時期に来ています。
子どもを守るため、そして教員を守るため、防犯カメラ設置の義務化を本格的に議論すべきではないでしょうか。
参考・引用記事
-
毎日新聞「教室に防犯カメラ、教育委員会の8割『検討せず』 教員の性暴力対策」
https://news.yahoo.co.jp/articles/7b977ffe99a84af67f5da55a45614d75b258dcf6 -
教育新聞「『教員の萎縮につながる』 SNS制限や防犯カメラ設置などに懸念」
https://www.kyobun.co.jp/article/2025072203 -
こども家庭庁「子ども性暴力防止に関する横断的指針」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0edff80e-78f3-4ce9-beb0-8940a26008cf/6a6ba71e/20250417_policies_child-safety_efforts_koseibouhou_odanshishin_01.pdf

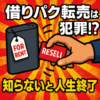
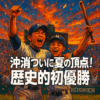
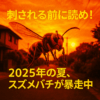
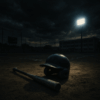
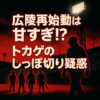
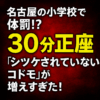
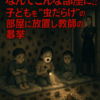




最近のコメント