【6月の食材】旬のオクラ大解剖!ルーツと日本の産地ランキング
オクラは、夏に旬を迎える緑黄色野菜の一つで、独特のネバネバした食感が特徴です。
和食から洋食、中華、エスニック料理まで幅広く活用され、栄養価が高いことでも知られています。
特に6月は市場に新鮮なオクラが多く出回り、食卓に取り入れる絶好のタイミングです。
オクラの魅力は、その粘りに含まれる 「ムチン」 という成分にあります。ムチンは胃の粘膜を保護し、消化を助ける働きがあるため、食欲が落ちやすい夏場にはぴったりの食材。
また、 食物繊維が豊富で腸内環境を整える効果 も期待されており、健康維持にも役立ちます。
さらに、オクラはカロリーが低く (100gあたり約30kcal) 、ダイエット中の方にもおすすめです。
βカロテンやビタミンC、カリウム、カルシウムなどの栄養素も多く含まれており、美容や健康にうれしい効果がたくさんあります。
本記事では、オクラのルーツや歴史を紐解きながら、日本国内の主要産地についても詳しくご紹介します。
オクラの生い立ちや、どこで育てられているのかを知れば、いつものオクラがより特別に感じられるかもしれません!
オクラのルーツと歴史:どこから来たのか?

原産地はアフリカ!古代エジプトでも栽培されていた?
オクラの原産地は、アフリカ北東部(エチオピアやスーダン) とされており、古代から人々に親しまれてきました。
特に 古代エジプト では紀元前2000年頃にはすでに栽培されていたという記録が残っています。
エジプトでは、オクラの種子を乾燥させて粉末にし、スープやシチューに加える食文化があったとされています。
また、ナイル川周辺では豊富な水資源を活かしてオクラを栽培し、人々の重要な食料源となっていました。
世界へ広がったオクラ!アジア・ヨーロッパ・アメリカへ
オクラは、エジプトを中心に 中東やインドへ伝わり、16世紀頃にはヨーロッパへも広がっていきました。
特に温暖な気候の地域で栽培が広がり、 インドではカレーの具材、地中海沿岸ではスープや煮込み料理に活用されるように なりました。
また、17世紀の奴隷貿易の時代には、オクラがアフリカからアメリカへと持ち込まれ、アメリカ南部の料理「ガンボスープ」の主要食材として定着しました。
現在でも、ルイジアナ州やフロリダ州ではオクラの生産が盛んです。
日本への伝来と普及の歴史
オクラが日本に伝わったのは 幕末から明治時代 にかけてのこと。
しかし、当時の日本ではあまり受け入れられず、一部の家庭で栽培される程度でした。
その理由の一つに、オクラ特有の 粘りが「馴染みのない食感」として敬遠された ことが挙げられます。
日本で本格的にオクラが普及し始めたのは 1960年代以降 で、アメリカから改良された品種が導入され、徐々に生産が拡大しました。
特に九州地方を中心に栽培が広まり、今では 日本の夏の定番野菜 の一つとして親しまれています。
日本のオクラ主要産地ランキングTOP5!
オクラは温暖な気候を好むため、日本国内でも 南の地域を中心に栽培 されています。
ここでは、 生産量の多い主要産地をランキング形式でご紹介します!
1位:鹿児島県(全国シェア約41.6%)
鹿児島県は 日本一のオクラ生産地 で、特に 指宿市 や 南九州市 での栽培が盛んです。
温暖な気候を活かし、 露地栽培・ハウス栽培の両方が行われており、年間を通じて安定供給 されています。
指宿産のオクラは「指宿オクラ」というブランド名でも販売され、 粘りが強く、やわらかい食感 が特徴です。
2位:高知県(全国シェア約16.1%)
高知県では、 宿毛市(すくもし)や四万十市での栽培が盛ん で、特に 皮が薄くて食感が良いオクラ が生産されています。
市場では「高知オクラ」として評価が高く、全国的に流通しています。
3位:沖縄県(全国シェア約11.3%)
沖縄県では 「丸オクラ」 という独自の品種が栽培され、 角がなく、柔らかくて甘みがある のが特徴です。
暑さに強く、 4月〜12月まで長期間収穫 できるのも魅力の一つです。
4位:熊本県(全国シェア約6.7%)
熊本県は 品質管理の徹底 に力を入れており、 病害虫対策を強化した安定した供給体制 を誇ります。
5位:宮崎県(急成長中の産地)
宮崎県では近年 オクラの生産面積が拡大 しており、 甘みが強く、食感がシャキシャキしたオクラ が育てられています。
オクラの魅力と今後の展望
オクラは 日本各地で生産され、品種や栽培方法も多様化 しています。
特に 鹿児島・高知・沖縄・熊本・宮崎 の5県が主な産地として市場を支えています。
6月から旬を迎えるオクラを、ぜひ食卓に取り入れてみてください!



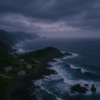


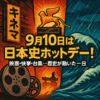
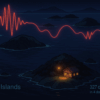




最近のコメント