【7月の行事】風物詩・土用干しの由来と実践方法を解説
日本には四季折々の風物詩があり、暮らしに根ざした行事が多く存在します。
その中でも「土用干し(どようぼし)」は、夏の暑さを活かした実用的な風習として、古くから人々に親しまれてきました。
梅干しを天日で干す工程として知られる土用干しですが、実はそれだけに留まりません。
書物や衣類、農業の田んぼにも「干す」という文化が深く関わっており、日本の気候や生活様式に密接に結びついています。
この記事では、「土用干しとは何か」という基本的な定義から始まり、その歴史的背景、具体的な実践方法、そして現代の暮らしにどう取り入れるかまでを詳しく解説します。
伝統文化に関心のある方はもちろん、生活を整える知恵を取り入れたいという方にも役立つ内容です。
土用干しとは?夏に行う理由
土用干しとは、土用の期間中に行われる“物を干す”という風習のことを指します。
特に夏の土用(例年7月20日前後〜8月6日頃まで)は、梅雨が明けて高温かつ乾燥した日が続くため、物を乾かすには絶好のタイミングとされてきました。
この土用の時期には、昔から食料や衣類、日用品などを風にさらし、湿気や虫の害を防ぐ目的で干されてきました。特に以下の3つが代表的です。
-
梅干し:塩漬けした梅を天日干しして殺菌・風味の向上・長期保存を可能にします。
-
衣類や書籍:タンスや蔵にしまってある着物や古文書などを虫やカビから守るために干します。
-
田んぼ:中干しと呼ばれる作業で、田んぼの水を一時的に抜き、稲の根を鍛え収量を安定させます。
このように、土用干しは一見単純な「干す」作業に見えますが、実は自然環境と暮らしを調和させた知恵の結晶です。
現代の除湿器や乾燥機がない時代、自然の力を最大限に活用した生活技術だったのです。
土用干しの歴史と広まり
土用干しの起源は非常に古く、奈良時代の正倉院文書にも関連する記述が見られます。
当時、皇室の宝物を陰干しする「曝涼(ばくりょう)」と呼ばれる行事がありました。
これは、湿気による腐敗やカビを防ぐために、書物や衣類を定期的に風通しの良い場所で干すというもので、現代の虫干しの原型とも言える儀式です。
平安時代になると、この習慣は宮中の文化として定着し、貴族たちは着物や書簡、調度品などを丁寧に干すことで、大切な物を長く使う工夫を凝らしてきました。
江戸時代に入ると、保存食の代表である「梅干し」が庶民の間でも作られるようになり、土用干しが広く一般化します。
各家庭で梅雨が明けると、梅をザルに並べて天日で干す光景が町なかの至る所で見られ、夏の風物詩として完全に定着したのです。
また、商家では帳簿や書物を虫干しし、農家では田んぼの水を抜いて乾かす「田の土用干し」を行うなど、それぞれの職業や地域性に応じて、多様な形で土用干しが取り入れられてきました。
梅干しの土用干し:基本のやり方とコツ

梅干しの土用干しは、日本の食文化の中でも特に奥深い技術です。
単に塩漬けしただけではなく、太陽の光と風の力を借りて仕上げることで、味や保存性が大きく変わります。
手順の詳細
-
塩漬け:6月頃に塩と赤紫蘇で漬け込んだ梅を準備します。
-
干す時期を選ぶ:7月下旬から8月初旬、晴天が3日以上続きそうな時期がベスト。
-
干し方:
-
梅をザルやすだれに並べ、朝から夕方まで天日に当てます。
-
途中でひっくり返して両面均等に乾かします。
-
夜間もそのまま干し、夜露に当てることで風味が増すとされています。
-
成功させるポイント
-
強すぎる直射日光は避ける(表面が固くなりすぎるため)
-
梅が重ならないように間隔を空けて並べる
-
赤紫蘇も一緒に干して、香りを引き立てる
この工程を丁寧に行うことで、保存性が高まり、梅の旨味と酸味のバランスが整った“極上の梅干し”に仕上がります。
完成後は殺菌した瓶や壺に入れ、常温保存でも数年は持つことから、まさに日本の知恵と風土が融合した伝統食といえます。
衣類や書籍の土用干し:家庭でできる虫干し
「土用干し」という言葉を聞くと梅干しが最初に浮かびますが、実は古文書や衣類にも深く関係しています。
高温多湿な日本の夏は、カビや虫にとって最適な環境。これを防ぐために、昔の人々は衣装蔵や文庫の整理に土用干しを活用してきました。
実践方法
-
衣類の場合:
-
ハンガーにかけて直射日光の当たらない風通しの良い場所に干します。
-
絹やウールなどは特に湿気に弱いため、日陰干しが基本です。
-
-
書籍の場合:
-
風通しの良い部屋で、書籍を立ててページを少し開いた状態にします。
-
ビニールカバーは外し、湿気を逃がすように配置するのがコツです。
-
注意点
-
湿度の高い日は避ける
-
和紙や古文書は直射日光に弱いため、陰干し必須
-
作業時間は1~2時間程度で十分
現代ではエアコンや除湿機が普及していますが、大切な衣類や本を守るために、自然な方法での虫干しを年に一度でも取り入れる価値は十分にあります。
田んぼの土用干し:農業における知恵
「田んぼの土用干し(中干し)」は、農業における非常に重要な工程です。
稲作では、苗がある程度成長した後に一度水を抜いて田んぼを乾燥させることで、根を鍛え、病害虫の発生を防ぐ効果があります。
なぜ水を抜くのか?
-
根に酸素を供給し、土壌の微生物活動を活性化させる
-
根の張りが良くなり、台風や雨による倒伏を防止
-
土壌病害を抑制し、健全な生育を促進する
この中干しは、梅雨明け後の土用の時期が最適とされ、農家は天候と稲の成長を見ながらタイミングを見極めて行います。
水を張り続けるだけではなく、「干す」ことで作物の力を引き出すというのは、自然と対話してきた日本農業の知恵そのものです。
現代に活かせる土用干しのアイデア
土用干しの文化は、決して過去の遺物ではありません。今の時代でも十分に役立ち、暮らしに潤いを与える習慣として見直されています。
生活に取り入れる方法
-
梅干し作りを夏の家庭イベントとして楽しむ
-
クローゼットの中の服を陰干しし、防虫対策と消臭に
-
古い本やアルバムを年1回虫干しすることで長持ち
-
夏休みの自由研究として「土用干し体験日記」をつける
自然の力を使って「整える」生活は、SDGsやエコ意識の高まりとも相性が良く、親子で学びながら取り組むきっかけにもなります。
手軽に始められる土用干しから、あなたの暮らしを少しだけ昔ながらの知恵で豊かにしてみてはいかがでしょうか。






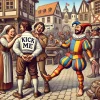





最近のコメント